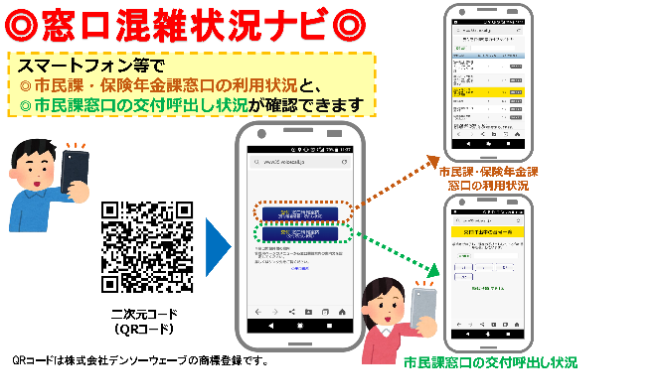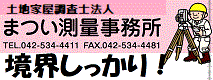平成19年度 第21回市民の会議・会議の要旨
更新日: 2008年(平成20年)2月25日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成20年2月9日(土曜) 午後2時~5時10分
会場
健康センター第1集会室
参加者数
23人(欠席者32人)
傍聴者:2人
配付資料
- 1月26日市民の会議全体会議事要旨
- 2月5日運営委員会議事要旨
- 2月2日学習会記録(未定稿)
- 前文案(2案)
- 都市内分権に関連した自治体の事例
- コミュニティについての討議にあたっての論点(再配布)
- 地域コミュニティとテーマコミュニティについてどのような位置づけで整理するか(再配布)
- 基本理念、基本原則案
- 基本理念基本原則他市事例
- 起草グループ条文案(市民・参加協働、市民投票)
会議結果の概要
1.進め方と日程について
1運営委員会報告
(2月5日運営委員会議事要旨の説明を行なった。以下、概要)
- 定義、基本理念、基本原則、権利、住民投票についての考え方の報告あり。「基本理念、基本原則」については本日議論。コミュニティについては、本日の議論を経てまとめる。
- 前文について、前文グループから本文および解説2案の提案があり、本日、具体的に内容を検討。
- 広報の発行は、今後は、これまでのように毎月20日発行ということにこだわらずに、何か動きがあった段階で発行することとした。
- これからの進め方の運営委員会提案として、期日が迫ってきたので、当面、全体会・運営委員会を月4回開催のペースで行うことを提案したい。
【進め方の了承】
- 運営委員会の提案を了承する。
- 運営委員会と全体会を同日連続で行う場合には、運営委員会を前半の1時間を活用して拡大運営委員会とし、全体会で参加できるメンバーは拡大運営委員会から参加し、運営委員会で決まった事項は、全体会で決定したものとみなすこととする。
【日程の決定】
- 2月14日(木)運営委員会+全体会 18時から
- 2月23日(土)全体会 14時から
- 2月29日(金)運営委員会+全体会 18時から
- 3月8日(土)全体会 14時から
- 3月14日(金)運営委員会+全体会 18時から
- 3月22日(土)全体会 14時から
- 3月30日(日)全体会 14時から
2.前文の本文部分について
- 下から6行目「・・・、学びと仕事と暮らし、・・・」の修正意見3つを含めて、参考としての賛否を取った。
原文 ・・・、学びと仕事と暮らし、・・・ (7人)
- ・・・、暮らし、学びと仕事、・・・ (2人)
- ・・・、暮らしと学びと仕事、・・・ (3人)
- ・・・、暮らしと仕事と学び、・・・ (5人)
- 下から2行目、「今ここに・・・」について修正が3つでた。原文を含めて、修正意見にたいして参考に賛否をとった。
原文 今ここに、・・・ (3人)
- よって、今ここに・・・ (6人)
- よって、今ここに私たちは、・・・ (3人)
- 今ここに私たちは、・・・ (6人)
【まとめ】
- 今日の意見を参考に、前文グループが案を作成する。また、1枚まとめの説明文の上から11行目「・・・多くの人口が流入し、・・・」の流入は、転入などの言葉に代えたほうがよい、「流入」の言葉の使用を含めて検討する。
3.地域コミュニティについて
- 第一部会の過去の議論を踏まえて意見を整理する、として、第一部会から報告。
- 地域型・テーマ型ということが論点ではない。
- 第一部会でのコミュニティを論点は以下のことである。
【第一部会での議論】
- 市民は市政に信託し、参加と協働で小平市の自治の運営を行うことについては、骨子案に既に明らかになっている。このことは、市全体の自治は自治法で定められている。
- このことを前提に、より小さな単位で地域自治を目指すことを考え、そのような場を、地域コミュニティ位置づけた。
- 即ち、全市一律のテーマ型は、より小さな単位で地域自治を目指すことにはならない。
【考え方の整理】
- 全体の自治に対して、住民自らが身近な地域から自治を形成することを考えている。その場を地域コミュニティとした。自治会町内会に限定しているわけではない。
- 地域自治とは参加の問題である。市民が参加し意見を表明し、計画や政策に影響を及ぼすことが参加である。しいては、防災や福祉などについて、ある領域の地域課題に対し、地域住民が責任を持って意志決定し、行政権限や財源等の一部を移譲し、自主的に解決する。そのような自治の形成を目標に、今出来ることを準備する、これが、条文の考え方だ。
- そのため、地域の課題やまちづくりを地域住民が熟議していく場が必要で、それを地域から作ること、即ち、地域の自治の場をつくることがこの条文の狙いである。
【論点の整理】(添付ファイル)
【意見】
- 自治会・町内会について、今の市の既設の自治会町内会は期待できない。
- 現在、取組が進められている新宿区では、より広い連合自治会程度の広がりで自治の育成を考えている。地域自治の育成を考えていくことが必要で、市民への意識啓発などを積極的に行うことは行政の役割。
- 地域活動に参加しない自由もあり、それへの配慮も必要。
- 組織を造る、造らないではなく、地域から自治への参加の場を設けるかどうかが重要な視点で、設けるような方向で考えることが必要と思う。
【まとめ】
- 考え方として、将来「より小さな地域自治の形成を目指す」考え方には賛同する。
- それを、どのように表現するかは検討の余地がある。
- 本日の議論を踏まえて、今後、骨子案をベースに議論していく。
4.各条文について
(1)理念、原則の説明
- 豊島区の条例では、目的⇒理念⇒原則という流れになっている。大体このような流れになると思う。
- 理念は、自治のビジョンを示し、原則は手段と考えることが出来、そのような考え方で文案を作ってみた。
- 理念に男女共同参画が自治の形成に重要は要素と考え、また、昼間部会からの強い意見でもあり記述した。
【市意見】
- 理念・原則部分は非常に大事な部分、条文全体の一貫性が求められる。
- 理念は、自治に特化し、参加・協働・市民自治のまちづくりを記述した方がよいと考える。
- その結果としてのまちの姿は前文でしめす。
- 今回の前文はそのような内容になっている。
【意見】
- 理念は、自治を進めるに当たっての考え方(理想像)、原則は理念を進めるに当たっての基本的な手段、ツールと考えられることで良いと思う。
- 理念の書き方によっては、骨子案#4との関係も出てくる。一緒に考えるのがよい。
- 骨子案#4の「幸福追求権」は、憲法の上乗せ施策を小平で考えることが前提となるので、要検討することを併せて必要。
- 今回のものに、男女共同参画が理念に記述されているのはよいと思った。
- 男女共同参画を理念に入れるのには違和感がある。
- 今回の理念の文案にある、男女共同参画社会は、自治の結果としての社会のあるべき姿を言っているので、前文の中に含まれると思う。
- 市民本位の市政運営を記述してほしい。
【まとめ】
- 理念は、自治を進めるに当たっての考え方(理想像)、原則は理念を進めるに当たっての基本的な手段、ツールと考えられ、その考え方で整理する。
- 簡素な表現とする。
- 次回までに、今日の意見を基に、たたき台を作る。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。![]()
Adobe社のサイトからダウンロードできます。(新規ウィンドウが開きます)