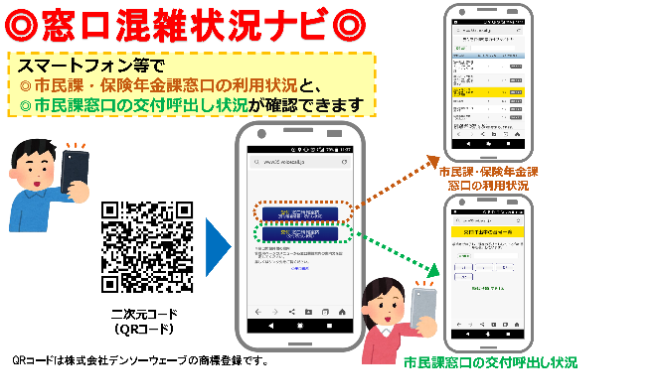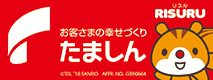平成19年度 第25回市民の会議・会議の要旨(1)
更新日: 2008年(平成20年)3月18日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成20年3月8日(土曜) 午後2時~5時
会場
福祉会館第1集会室
参加者数
24人(欠席者30人)
傍聴者:3人
配付資料
- 条例案のイメージ
- コミュニティ関連の各案と参考資料
- 市民投票部分条文案
- 自治基本条例における市民投票の規定について
- 平成20年2月29日市民の会議・会議の要旨
- 「自治基本条例だより第11号」
会議結果の概要
1.報告事項等
(1)市議会傍聴の報告
- 現在行われている市議会の予算特別委員会にて、企画政策部関連で自治基本条例についての質疑がされたので、傍聴したメンバーから報告があった。
(2)その他
- 平成20年3月末日をもって、地域総合計画研究所と市との契約が終了するため、3月30日の全体会終了後に送別会を開催したく、準備を進める。予定の合う方はぜひ出席いただきたい。
2.コミュニティ
○条文案提案者(メンバー)
- 前回に提案された条文案およびそこでの結論をうけて、表現を整理したので提案する。
(コミュニティ活動)
第5-1条 市民は、住みよい地域社会を築くため、市内のそれぞれの地域において、地域を基盤とした、又は一定の目的を持った組織又は集団によるまちづくり活動(以下「コミュニティ活動」といいます。)を行うことができます。
2 市民は、コミュニティ活動において、市に対しまちづくりに関する意見を表明することができます。
- 「コミュニティ」を組織ではなく活動として捉えるという考え方がわかりよく適切だと考え、条のタイトルおよび条文には「コミュニティ活動」という表現を採用した。
- 第1項は、憲法第21条(集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由)に保障される権利の確認的な規定であり、新しい権利の創出ではない。
- では、コミュニティについて条文化する大きな意味があるのは、コミュニティと市との関係をどうするか、という点である。今回はその部分の条文を提案していない。
1 「自主的」という表現について
- この規定は、集会、結社、その他表現の「自由」の確認的規定である。自由な活動が自主的であるのは当然であるので削除した。
2 「地域課題の解決」という表現について
- 骨子案にあった「地域の課題に取り組み」などの表現があったほうが、具体的に何に取り組むのか分かりよいのでいい。
- コミュニティが取り組む内容は「地域課題の解決」だけではない。たとえば、祭りなどもその取組み内容に含めたい。すると「地域課題」だけでは狭いように思う。
3 「合意形成をはかる協議を行う」について
- 「合意形成をはかる」という表現の意味が不明瞭であるし、また、憲法第21条の集会結社、その他表現の自由に含められると考えられるので削除している。
【合意形成は必須である】
- 合意形成を図ることは必須事項だ。コミュニティとは、市に意見を表明するあるいは、コミュニティ内で施策を実施するための場であり活動である。このような意味でサロン的な活動とは分けて考えるべき。
【代表性のないコミュニティによる「地域の課題についての合意」には問題あり】
- コミュニティが地域を基盤とした活動を行うにあたって、そこで合意された事項がその他の人に対しても強制力を持つことを懸念する。自主的に集まったコミュニティに正当性、代表性はない。強制するつもりがなくても、「無言の圧力」を発するということはままあることだ。
【協議し意見表明することが大切】
- 決定事項に強制力をもつような権限をコミュニティに与える意図はない。ただ、協議し意見を表明することが大切である。
4 条文案としての到達点を考える
- これだけ議論をしてきた現時点においても、市民の会議の中でもコミュニティについての考え方や価値観が分かれている。コミュニティの役割や機能について、具体的に決めることは難しいのではないか。
- 「コミュニティ活動」の定義と、「市はコミュニティ活動に対して適切な施策および支援を行う」旨のみ規定し、「協議、合意形成、意見表明」といった具体的な内容は規定しないことにしたらどうか。
【まとめ】
- コミュニティについては、(コミュニティ活動の定義)+(コミュニティ活動に対する市の支援)のみが、最低限、合意できる内容である。
- この内容で起草グループが条文案を作成する。
3.市民投票制度
【市民投票の規定を置く主旨とは?】
- 市民投票は間接民主主義を補うもの、市民が直接意見表明する場として必要である。
- まず、「市民投票ができる」という宣言、確認をするために規定したい。
- その上で、その結果の尊重をうたう必要がある。
- 実施の方法は「別に定める」としてもいいと考えている。そうすると常設型かそうでないかも含めて議会にゆだねられることになる。
【どのように規定するか】
- 議決を必要とする方法では、なかなか実施できないので常設型がいいと思うが、ただし、連署数のハードルを3分の1など高く設定する必要がある。
- 実際には動かない条文というのは意味がないと考えるが、それでも、自治基本条例のシンボル的存在として、確認規定のみでも規定したい。
【まとめ】
- 市民投票制度については、「市民投票が実施できる旨の確認」および「結果の尊重」のみを規定し、常設型とは限定しない、とする意見が多数であることを確認した。
- 次回以降も引き続き議論を行う。
議事録
今日の進め方(全体会)
1.報告事項等
(1)前回のおさらい
(2)市議会傍聴の報告
(3)その他
2.コミュニティ
3.市民投票制度
1.報告事項等
(1)前回のおさらい
○代表
- 前回は、運営委員会はほとんど時間をとらず、全体会にて1.市民投票制度、2.オンブズマン制度、3.コミュニティについて議論した。
- 市民投票制度については本日も議論する。オンブズマン制度については、行財政の部分について市との協議を行う際に合わせて継続議論することとした。
- コミュニティについては、前回のまとめをうけてメンバーから条文案の提案があるので、本日はそれをもとに議論する。
(2)市議会傍聴の報告
○代表
- 現在行われている市議会の予算特別委員会にて、企画政策部関連で自治基本条例についての質疑がされたので、傍聴者からご報告願いたい。
○メンバー
- 紹介のあった3月1日の委員会の前日、2月29日にも条例について意見があったのでご報告する。
- 「35人学級を市長が公約に掲げているのにまだ取り組まれていない。同じ公約に掲げられた自治基本条例は取り組んでいるが、どちらがより生活に密着した課題なのか?」という意見が出された。
- 予算特別委員会では、市議会議員から以下のような質問が出された。
- 「『市民』の定義を明確にして条例の中身を作るべきである。市長はどのように考えているのか。」
- 「多くの市民は条例作成の動きについて知らず、まだ機運が高まっているとは言えないのではないか。」
- 「自分も市民であるので意見が言いたいがどのような方法で言ったらいいのかわからない。」
- 最後の意見については、これまでも多くの方法を設けていつでも意見を言えるようにしてきているので残念に思った。
(3)その他
○代表
- 以前から何度かお話しているが、平成20年3月末日をもって、地域総合計画研究所と市との契約が終了する。市民の会議としては、契約を延長して最後まで支援してもらいたいが、市の平成20年度予算はつかない結果となった。
- 3月30日の全体会終了後に送別会を開催したく、準備を進めたい。予定の合う方はぜひ出席いただきたい。
2.コミュニティ
○条文案提案者(メンバー)
- 前回に提案された条文案およびそこでの結論をうけて、表現を整理したので提案する。
【提案】
(コミュニティ活動)
第5-1条 市民は、住みよい地域社会を築くため、市内のそれぞれの地域において、地域を基盤とした、又は一定の目的を持った組織又は集団によるまちづくり活動(以下「コミュニティ活動」といいます。)を行うことができます。
2 市民は、コミュニティ活動において、市に対しまちづくりに関する意見を表明することができます。
- 「コミュニティ」を組織ではなく活動として捉えるという考え方がわかりよく適切だと考え、条のタイトルおよび条文には「コミュニティ活動」という表現を採用した。
- 第1項は、憲法第21条(集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由)に保障される権利の確認的な規定であり、新しい権利の創出ではない。
- では、コミュニティについて条文化する大きな意味があるのは、コミュニティと市との関係をどうするか、という点である。今回はその部分の条文を提案していない。