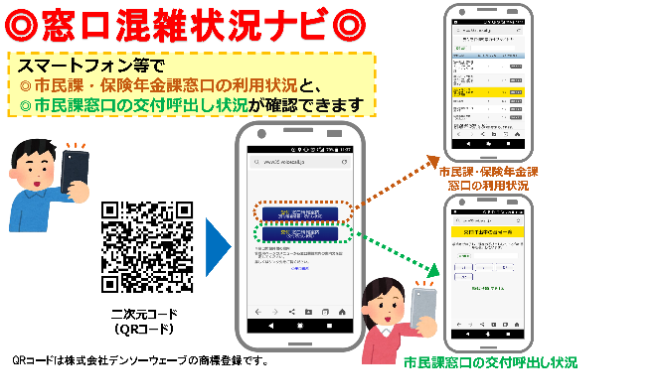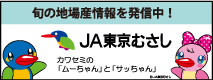平成20年度 第29回市民の会議・会議の要旨(1)
更新日: 2018年(平成30年)6月18日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成20年4月5日(土曜) 午後2時~7時15分
会場
健康センター視聴覚室
参加者数
25人(欠席者29人)
傍聴者:1人
配付資料
- 市民の会議・会議の要旨(平成20年3月30日(日))
- 第35条自治推進委員会のメンバーからの代替案
- 小平市自治基本条例をつくる市民の会議の活動および「自治基本条例市民案」発表会開催のお知らせ(代表の呼びかけ文)
- 第二次市民意見交換会広報用のチラシ見本
会議結果の概要
1 広報グループの報告
- 第二次市民意見交換会の参加呼びかけのチラシは、配布資料のようにする。
- 発行はできたら、2週間前ぐらいを目処にする。
- チラシ配布だけでは参加が少ないので、メンバーのみんなで声掛けを行う。
2.5月10日の市長への条例案提出の時間設定
- 平成20年5月10日 15時~17時
3.条例案検討
3-1 第8章から第10章まで
○代表
- 第8章24条以降は市との意見交換が十分行われていない部分であり、市から具体的な意見を聞き、そして、意見交換・調整をすることで進める。
○市意見
- 市として意見のあるところは、第25条2項、26条、27条(1)号、29条2項、30条2項、31条、33条、34条1項と6項、38条
1)第25条2項(基本計画の議決について)
- 今までの意見をまとめると、検討案として
1.原案通り(賛成1名)
2.2項削除(賛成8人)
3.表現を変えて残す(賛成13名)となる。
- この意見を受け止め、市も持ち帰って検討する。
2)市の「議決対象は議会で決めることで、市執行部として提案しづらい」とのことについて
- 市民側から提案された条文案と考えれば、何も問題がないのではない。そのように取り扱い、市執行部や議会に説明して欲しい。
3)第26条について(組織と人事)
- 1項は、「横断的」を削除。
- 2項について、以下の案で考え、市、持ち帰り検討する。
「市は、その組織が、市民のための政策の企画立案に当たり、先見性と創造性を発揮できる人材集団として機能するよう、職員の採用及び能力開発に取り組みます」
4)第27条(1)号について(情報の共有)
- 「複数の方法で」の表現を変えて、[1]かつ入手し易い方法で、[2]多様な方法で、[3]出来るだけ・・・、などを参考に、市、持ち帰り、検討する。
5)第29条2項(オンブズマン等第三者機関)
- オンブズマンを削除し、「第三者機関等」としても具体的な説明が難しいと思うが、市持ち帰り検討する。
6)第30条2項(市民を含む外部者による評価)
- 案「外部の意見を取り入れ、客観性、透明性の確保に努めます」で、市持ち帰り検討する。
7)第31条(危機管理)
- 意見が3つのケースに絞り込まれたので、それを基に対応することにしたい。
・案 1.削除する(賛成11名)。
2.災害時、震災時の対策に絞って表現を変えて残す(賛成10名)。
3.原案通り(賛成0名)。
- 市は、この意見を尊重して、持ち帰り検討する。
- 有志メンバーに、2を基に、表現を考えてもらう。そして突合せする。
8)第33条(政策法務)
- 政策は大事で、政策の実現を法務が保障する。法令化することで組織は動くので、必要な条文と思う。
- 市は法務能力が必要、議会はもっと法務能力が重要と思い、議会にも記述した。
- 市としては、ここは皆さんの意見を知りたかったので、今の意見を持ち帰り検討する。
9)第34条(財政のあり方)
(1)1項
- 「・・・財政状況を総合的に把握し、それを分析することにより、市民サービスの質を向上させ、・・・」の「それを分析することにより、市民サービスの質を向上させ、」を削除。
(2)6項
- ( )書きの「25%以上」とした骨子の意図が判ったので、市調べて検討する。
10)第35条(自治推進委員会の設置)
- 前回も大分議論したが、皆の考える方向性は
1.原案通り(賛成7人)
2.メンバー案(賛成1人)
3.削除(8人)
- 削除にするにしても、第二次市民意見交換会でその理由をどのように説明するかは問われている。まだ、整理が付いていない。
- これを受けて、引き続き検討、市も検討。
11)第38条(国際的な関係)
- 高齢化社会の中で、介護補助に外国の人を頼むことや環境の取り組みなど、国際的な関係は数年後には具体的な問題となる。
- 具体的な例示を示して残す。
- メンバー有志が、対案を考え次回提案。
議事録
【議題】
1.広報グループの報告
2.5月10日の市長への条例案提出の時間設定について
3.条例案検討
3-1 第8章行財政運営のあり方、第9章国、都等との関係、第10章条例の位置付けと見直し
3-2 第3章参加と協働
4.その他
【会議内容】
1.広報グループの報告
- 第二次市民意見交換会の参加呼びかけのチラシは、配布資料のようにしたい。
- 発行はできたら、2週間前ぐらいを目処にしたい。
【全員承認】
2.5月10日の市長への条例案提出の時間設定について
○代表
前回の全体会(3月30日)で決定した市長への条例案の時間を16時~17時としていたのを、1時間早め15時~17時としたい。理由は、委員メンバーの条例策定をこの2年間行い、いろいろな思いや条文に示された内容の実施など市長にも伝えたい。また、市長の考えも聴きたい。と言うことから、単なるセレモニーに終わらすのでなく、意見交換ができるようにしたい。そのため、時間もとるということで、1時間スタートを早め15時スタート、17時終了の2時間とした。いかがか。
【決定事項】
平成20年5月10日 15時~17時
3.条例案検討
3-1 第8章から第10章まで
○代表
- 第8章24条以降は市との意見交換が十分行われていない部分であり、市から具体的な意見を聞き、そして、意見交換・調整をすることで進める。
○市意見
- この部分については、一括して市として意見のある項目を始めにお話しして、各条文検討の際に詳しく意見をのべることにしたい。
- 市として意見のあるところは、第25条2項、26条、27条(1)号、29条2項、30条2項、31条、33条、34条1項と6項、38条
1)第25条(長期総合計画)2項
○市意見
- 「・・・・・・総合計画のうち、基本計画についても市議会の議決・・・・」の「基本計画」についてもが問題を感じている。
- 理由は、[1]基本構想は法に定められ、既に議会で議決している。[2]「基本計画」を議決対象にするかは、議会で決めることで、市執行部として提案しづらい。
- 現基本構想は15年間の計画、基本計画は、前期基本計画として10年間の計画、後期基本計画が5年間の計画。
- 現総合計画は市民参加で、3か年かけて策定した。
○メンバー
- この規定を設けないと、市長は議会に諮らずに進めていく可能性があると思う。
○メンバー
- 重要な計画は議決しないと実行があいまいになる。
○市意見
- 総合計画は市政運営のバイブルなので、議会が審議しないことは考えられない。質問も多く出るし、報告する手続きは行っている。議決を提案することが問題。
○メンバー
- 現状では、基本計画の作り方は、[1]策定段階で市民が参加できる方式、[2]シンクタンクへの丸投げ、[3]上位の国や都の意向を重視のどのような方法を小平は取っているのか。
○市意見
- 小平では、[1]は市民参加の場は審議会等で行っている、[2]は丸投げすることなく職員が実質内容を書いている、[3]は市が対等の立場で調整していて、国や都の言われた通りのものではない。
○メンバー
- 基本計画には市民参加の場がない、ないしは弱いのではないか。
○起草
- 総合計画等の重要な計画については市民参加の場を設けることを、第10条(1)号で、規定している。
○メンバー
- 今の計画策定は市民参加になっていない。それを議決は深めていくことになるのではないか。
- 基本計画は法で作ることを定められているものなのか。
○メンバー
- 定められてはいない。しかし、計画行政と言うことで基本構想⇒基本計画⇒3か年実施計画⇒予算とあり、最初の「基本構想」と最後の「予算」が議決要件になっている。中段が議決要件になっていないので、議決することのほうが良い。
○市意見
- 実務的には問題ないが、自治法で定められていないものを規定するのはどうか。
○メンバー
- 施策の実行を目的とした基本計画などの中・長期計画の場合、議決したほうが良いかは意見の分かれるところ。現代のように変化が激しいときに、計画を変更して対応することは良くある。そのときに、議決対象では迅速な対応ができにくいという問題もある。