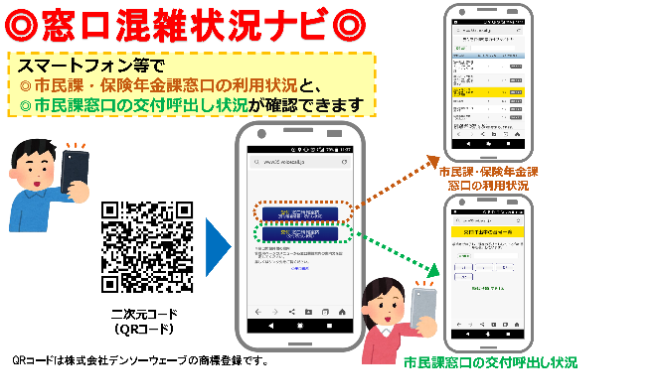平成20年度 第32回市民の会議・会議の要旨(1)
更新日: 2018年(平成30年)6月18日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成20年4月26日(土曜) 午後1時~9時
会場
健康センター視聴覚室
参加者数
30人(欠席者24人)
傍聴者:なし
配付資料
- 市民の会議・会議の要旨(平成20年4月19日(土))
- 自治基本条例市民の会議案(080426 起草案)
- (仮称)自治基本条例7つのポイント
- 市民意見交換会用条例案解説集
会議結果の概要
【会議内容】
1 市民意見交換会の進行について
2 条例案について
全条にわたり、確認をした。
【変更があったのは、以下の規定】
1)第3条
- (3)市民等の定義で、「学び、働き、又は活動」とあるのは、前文と揃えて、「働き、学び、又は活動する」とする。
- (5)参加の定義の「市民」を、「市民等」とする。
※(起草)立法技術的には、入れないとは思うが、入れても差し支えないと思う。ただ、記述の問題になるので、最終的には、市の法務担当との協議によると思う。
- 28条(苦情及び要望への対応)にも同様 「市民」は、「市民等」でもいいのではないのかと意見が出されたが、他の規定との兼ね合いもあるので、市の法規担当と調整するということとされた。
2)第4条(行政サ-ビスを受ける権利及び負担の義務)
- 「租税等により分担します。」をわかりやすい表現をという提案があり、「租税等により負担します。」とする。
3)第5条(市政に参加する権利)
- 第2項を前文と合わせ、「働き、学び又は活動する個人」とする。
4)第12条(協働の推進)
- 「協働を推進することができます。」を「協働をすることができます。」とする。
5)15条(コミュニティ活動)
- 「市民」を「市民等」とする。
6)16条(コミュニティ活動への支援)
- 「コミュニティ活動の役割を尊重し」を「コミュニティ活動の役割及び自主性を尊重し」とする。
7)29条(行政評価)
- 「第29条(評価・検証)市は、効率的かつ効果的に市政を運営するため、市政の取組みを評価・検証し、その結果を公表します。2前項の評価・検証については、外部の意見を取り入れ、その客観性及び透明性の確保に努めます。」とする。
【次回の協議事項としたのは、以下の項目】
1)第10条(参加の対象等)
- 除外規定、「税に関する条例等金銭徴収に関するもの」について
- 応答責任について
2)38条(条例の見直し)
- 条例の見直しについての市民参加条項について
3 条例案の解説について
- 市民の会議で条文案の解説をつくることに決定した。
議事録
【議題】
1.市民意見交換会の進行について
2.条例案について
3.条例案の解説について
1 市民意見交換会の進行について
- 全体説明15分
- 前文 5分
- 条例は、1条1分を目安として、前半、後半それぞれ20分とする。
- 質疑については、全体説明、前文時、前半終了時に行うこととする。
- 市民意見交換会で出された意見については、5月3日の全体会で検討する。
○起草グループ
- 市民意見交換会のための資料を作成した。「(仮称)小平市自治基本条例素案 7つのポイント」でこれで、今回の条例案の特色を7つ列挙してあるので、市民意見交換会の説明の際に参考にしてほしい。
2 条例案について
○代表
- 前回の全体会の積み残しもあるので、今回は、条例案について全条にわたり最終検討をすることとする。
1)前文
○前文検討グループ
- 前回の全体会以降に4人の方から、具体的な提案をいただき、4月22日に前文検討グループ会議を開催して、協議した。
- 「遥か先史時代から人々が暮らし」と前回の全体会で提案した部分については削除した。そして、前回提案した、「新田開発によって開け」については、そのままとした。
- 「持続可能」という言葉を削除という提案があったが、これは協議の結果残し、解説に詳述することとした。
- 本文については、以上のとおり。あと、解説の記述についての提案があり、それについても、反映させるよう協議を行った。
→了承
2)第1条(目的)
意見なし
3)第2条(自治の基本理念とその実現)
○起草グループ
- 前から意見のあった部分について4月21日に起草グループ会議を開催して、協議して変更した。
- 第1項は、「主権者として」を入れ、「市民は、主権者として市議会と市長に市政を信託するとともに、互いに協力して積極的にまちづくりに取り組みます。」とした。
- 第2項は、「市民の総意として」という文言がふさわしくないのではという意見が出されたので、「市民の信託に応え」とし、「市議会と市長は、市民の信託に応え、公正かつ適切に市政を行います。」とした。
- 第3項は、1項と2項が「自治の基本理念」で、これを実現するための方法なので、言葉を揃えた方がいいという意見を受けて、「市民、市議会及び市長は、情報共有、参加及び協働を基本的な指針として、前2項に掲げる自治の理念を実現します。」とした。
【出された意見】
1について
- 主権者とは、選挙権を有するということか。
- (起草) 基本的には、その自治体の中で本来の権利があるべきということ
- 市民を指すのは、子ども、外国人を含めてということか。
- 信託するということであれば、主権者ではないのか。
- ここは、理念的な規定であるので、限定的にとらえることはない。理念的、抽象的な主権者。主権者とは言っているが、有権者とはイコールではなく、子どもも潜在的な主権者という意味に解釈してもいいのではないか。
- 議会制民主主義だから、意思の確認できる有権者は、20歳以上ということになる。
- 選挙で信託するということと、それを補う意味で参加ということがあると思う。そういう意味では、ここを有権者ということで限定することはないのではないか。
- ここで、限定的に考えると、参加の規定の説明がむずかしくなる。
- この文の後半部分、「互いに協力して積極的にまちづくりに取り組みます。」は、主権者に限定したことではないと思う。
- 前半と後半を分けて、2つの文にすればいいのではないか。
- 白紙に読んだ時にどう取れるかということを考慮した方がいい。
- 主権者という言葉をここで入れると、理解の仕方が変わってくるし、限定的になるので、取った方がいいのでは。
- どう誤解なく、伝えるかということで全員の合意は取れたと思う。
【結論】
- 1については、5月3日の文言整理を協議することとし、意見交換会の資料には、この部分は掲載しないこととする。
- 2、3については、了承
4)第3条(定義)
○起草グループ
- (6)協働の定義については、「対等な立場で協議し合意の上」という文言は、第12条(協働の推進)とダブっているため削除した。
【出された意見】
- (3)市民等の定義で、「学び、働き、又は活動」とあるのは、前文と揃えて、「働き、学び、又は活動する」とした方がいいのでは。
→了承
- (5)「参加とは、市民が」とあるが、ここは「市民等」ではないか。
- 第5条(市政に参加する権利)の第2項で市民等について規定してあるので、市民でも問題ない。
- (6)協働も「市民等」となっているので揃えた方がいいのではないか。
- 起草(6)協働には、第5条に当る条文がないため、ここは「市民等」となる。立法技術的には、入れないとは思うが、入れても差し支えないと思う。ただ、記述の問題になるので、最終的には、市の法務担当との協議になると思う。
→了承
5)第4条(行政サ-ビスを受ける権利及び負担の義務)
○起草グループ
- 「租税等により分担します。」をわかりやすい表現をという提案があり、「租税等により負担します。」に変更した。
【出された意見】
- 今回の条例は、自治のあり方を規定するということであれば、この条項もなくてもいいのでは。
- ここで、規定していることは、今後どのような行政サービスをどのくらいの負担をして受けるかということを市民が選択していくことになると思う。そういう意味では、自治に深く関わることなので、残した方がいいと思う。
→現行の案のままとすることに決定。