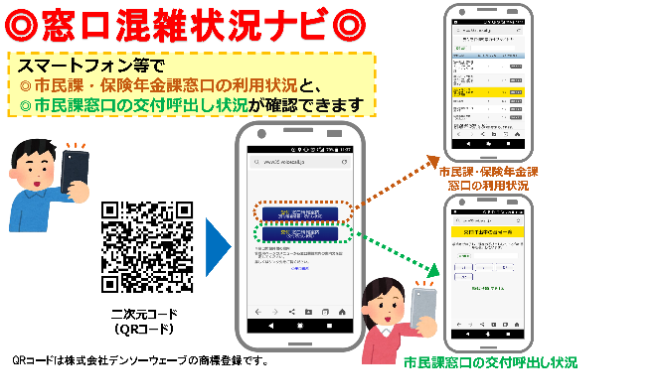高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種【65歳対象:費用一部助成】
更新日: 2025年(令和7年)4月1日 作成部署:健康福祉部 健康推進課
高齢者肺炎球菌ワクチンについては、65歳の方を対象に定期予防接種を実施しています。
対象者の方は、接種費用の一部を公費負担により、接種を受けることができます。
接種を受けるかどうかは対象者の任意となりますので、医師とよく相談し、接種の効果や副反応などを十分に理解したうえで判断をしてください。
なお、66歳以上の方を対象とした任意予防接種への一部費用助成は、令和7年3月31日限りで終了しています。
肺炎球菌感染症
肺炎球菌という菌によって起こる感染症です。肺炎球菌による肺炎は、特に高齢者や種々の基礎疾患(心臓・呼吸器の慢性疾患、腎不全、肝機能障害、糖尿病など)を有する方での重篤化が問題になっています。組織侵入性の感染を起こし、肺炎、髄膜炎、敗血症を起こすほか、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎などの原因となります。
肺炎球菌ワクチン
肺炎球菌という細菌を体内から取り除く働きのある抗体を事前に作り、肺炎などの感染症を予防するワクチンです。
このワクチンは肺炎球菌感染症全体の約70%に対応することができ、1回の接種で5年以上効果が持続するといわれています。
1回目に接種した後、5年以内に次の接種をした場合は、接種した部分が硬くなる、痛む、赤くなるなどの症状が強く出ることがあります。
肺炎球菌は予防接種法上のB類疾病に分類されており、予防接種は個人の発病又は重症化の予防に重点を置き、対象者本人が接種を希望する場合にのみ実施するものです(努力義務はありません)。
定期予防接種
対象者
市内在住で、過去に肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けたことがなく、次のいずれかに該当する方
- 65歳の方
- 60歳から64歳までで、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級程度)
助成金額
4,000円(税込)
- 令和7年4月1日から助成金額が変更となっています。
- 接種時に各医療機関の定める予防接種料金から、助成金額を引いた額をお支払いください。
- 生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付世帯の方については、9,900円(税込)を上限に助成します。
接種場所
(注)接種を受ける際は、事前に医療機関に問合せのうえ、来院してください。問合せの際は、小平市の費用助成を希望している旨をお伝えください。
(注)入院などのやむを得ない事情により、上記以外の医療機関等での接種を希望される場合には、必ず事前(2週間程度前まで)に健康推進課へお問い合わせください。
持ち物
- 高齢者肺炎球菌定期予防接種予診票
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、有効期限内の健康保険証・資格確認書など)
- 60歳から64歳までの方は、身体障害者手帳の写し
- 生活保護受給世帯の方は、生活保護受給証明書の原本
- 中国残留邦人等支援給付世帯の方は、中国残留邦人等支援給付証明書の原本
予診票
接種時は、専用の予診票が必要となります。
- 65歳の方には、誕生月の翌月(初旬ごろ)に予診票を個別に送付します。
- 予診票を紛失した場合などや、60歳から64歳までの方で対象者にあてはまる場合は、健康推進課までお申し込みください。
予診票交付の申込方法
窓口、電話、メール、インターネット(LoGoフォーム「予防接種予診票交付申請」(外部リンク))のいずれかの方法でお申し込みができます。
窓口でお申し込みの場合には、その場で予診票を交付します。
電話、メール、インターネットでお申し込みの場合には、郵送での交付となりますので、お届けまで2週間程度かかります。
任意予防接種への一部費用助成
66歳以上の方を対象とした任意予防接種への一部費用助成は、令和7年3月31日限りで終了しています。
予防接種に関する注意事項等
予防接種を受けることができない方
- 発熱していることが明らかな方(通常37.5℃以上)
- 重篤な急性疾患に罹患していることが明らかな方
- 当該ワクチンの成分によってアナフィラキシーを呈したことが明らかな方
- その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した方
予防接種を受ける前に医師への相談が必要な方
- 心臓血管系・腎臓・肝臓・血液などの基礎疾患のある方
- 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方、全身性発疹などのアレルギーを疑う症状がみられた方
- このワクチンの成分に対して、アレルギーを起こすおそれのある方
- 過去にけいれんを起こしたことのある方
- 過去に免疫不全と診断された方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- 血小板が少ない方や出血しやすい方
接種を受けた後の注意事項
- 接種後30分程度は急な副反応が起こることがありますので、医師とすぐ連絡がとれるようにしてください。
- 副反応は、接種部位の疼痛や発赤などが多いですが、稀にアナフィラキシー、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎様症状などが報告されています。
- 接種当日の激しい運動や大量の飲酒は避けてください。
- 接種部位は清潔に保ってください。入浴は差し支えありませんが注射した部位はこすらないでください。
- 接種後4週間は、副反応の出現に注意してください。接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
認定にあたっては、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会において、因果関係が認められるかを判断します。
詳しくは関連リンクをご覧いただくか、健康推進課までお問い合わせください。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。![]()
Adobe社のサイトからダウンロードできます。(新規ウィンドウが開きます)