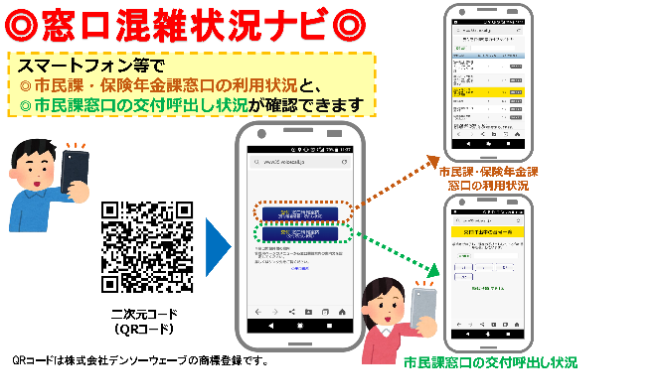第1部会 検討の記録 (6)
更新日: 2007年(平成19年)10月3日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成19年7月6日(金曜)、午後7時00分~9時15分
検討テーマ
- コミュニティについて
配布資料
- 「コミュニティについての資料」(岐阜県地方自治学校研修課)
検討の記録
1.コミュニティとは
- 国民生活審議会報告(昭和44年)の定義が分かり易い。「生活の場において市民としての自主性と責任を自覚した個人及び家庭を構成主体として、地域性と共通目標を持った開放的で、しかも構成員相互間の信頼感ある集団」
2.包括的コミュニティと機能的コミュニティ
1.包括的コミュニティとは
- ある地域を想定して、包括的にその地域のまちづくりを考え、行動する組織。
2.機能的コミュニティとは
- あるテーマ(福祉や防犯など)に関する課題を解決するための住民の集まり
3.包括的コミュニティか、機能的コミュニティか
1.地域の関心ごと
- 地域では、ごみ出しや防災・防犯は大きな関心ごと。
2.包括的コミュニティか、機能的コミュニティか
- コミュニティは本来、包括的な機能を持つものである。それが小平では不十分な状態で、見るべきものがない。現状は、住民が活発に活動しているのは個別機能の活動である。
- 小平は新しい都市。機能コミュニティがあれば、包括的コミュニティはいらないのではないか。
- 小平では機能的コミュニティがあればよしとするのでよいのではないか。
- 小平のような狭い市域では、地域を考える必要があるか。まちづくりの課題に地域性はないのではないか。
- やはり地域性があり、それによりまちづくりの課題は違っていると思う。
- 例えば、コミュニティバス開設の運動を行っているグループは、市西北の地域の人が多い。駅から20~30分かかる地域では大きな問題。個別課題にも地域性がある。
- 自治の基本単位としてのまとまりは必要と思う。
- 国民生活審議会の理念を抑えて、包括性を考える。
- コミュニティを考えるときには自治会・町会の役割は大きい。しかし、現在機能していないので、何か働きかけるか、新たに地域で作りかえるか、どうするかが大きな問題。
4.包括的コミュニティについて
1.地区割りと包括的コミュニティ
- 現在の住居表示などの行政区画と昔からの集落は合わない。
- コミュニティの区割りは、学校単位か。
- 区割りを条例で示して、住民に問うのか。
- 地域的なコミュニティを今後、住民が自覚的に作っていかないとだめだ。区域割りは難しいのではないか。
- 小平市の姿勢は、地域コミュニティ(主に自治会・町会を指す)は自主的な活動として、区割りは特別に考えていない。 ]
2.包括的コミュニティ形成の難しさと必要性
- 地縁のコミュニティをもっと魅力的なものにしたら良いと思う。包括的だから目的を見つけるのが難しいが。
- わたしのところの自治会は、現在は活発に活動しているが、きっかけは防犯活動だった。最初のきっかけは個別課題から出発するので、無理に包括的なテーマを見つける必要はないのではないか。
- 昔は子どもを通じて地域との接点があったが、子どもが大きくなって地域との関わりが薄くなっている。
- 都市が成熟化してきて、地域自治会の課題が変わってきた。しかし、活動は昔と変わらない。地域で新しい課題発掘と解決の方法を検討する必要に来ている。