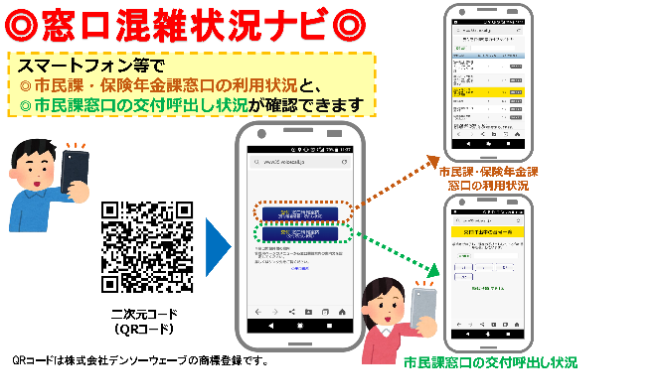第1部会 検討の記録 (7)
更新日: 2007年(平成19年)10月3日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成19年7月14日(土曜)、午後7時15分~9時15分
検討テーマ
- 地域コミュニティについて
配布資料
- なし
検討の記録
1.第一部会でのコミュニティについて出された意見のまとめ報告
- 「地域コミュニティ」を「地域包括的コミュニティ」と呼ぶ。機能的コミュニティを「機能テーマ的コミュニティ」と呼ぶ。
2.地域コミュニティについて
1.地域コミュニティの体制とは
- 最小限の組織体の確立が必要。
- 一時的な組織活動は地域コミュニティの核にはならない。その意味ではテーマ型が核になるのは難しいと思う。
- 今までの組織を活用することが必要。
- 町会・自治会は無視できない。
- 町会・自治会がないところでは誘導していくことが必要。しかし、町会・自治会は地域差があり、地域でそれを包み込むようなものが求められていると思う。
- 町会・自治会がないところは誘導していくことが必要。
- マンションでは管理組合が自治組織の役割を担っている。
2.基本単位の考え方
- 学校区で括ると、小平の発達段階ごとに特徴を持つ地域で括れる。
- 地域といっても課題によって広がりが違う。
- 課題によって広がりが違うものに対しては、基礎単位の地域が連携して対応すればよい。
- 小平では学校区より細かい単位で地域センターが配置されていて、その広がりでも良いのではないか。
- 地域は日常生活単位の視点が必要。
- 顔の見える範囲、声の届く範囲、歩ける範囲。
- 防災避難所は高齢者には遠い。
3.地域コミュニティの役割
- 地域のまちづくりを地域の視点で考える。
- 最小単位の場(施設の管理運営)、権限、責任を持たせる。
4.地域課題とは
- みんなの関心がある、安心・安全を核にする。
- 地域性の中に課題がある。
- となりの町会・自治会と性格や活動内容、課題が違う。地域の組織が連携するには、これを包含する共通の課題を見つける必要がある。
- 地域コミュニティは本来、包括的な機能を持つものである。
5.条例で何を表現するか
- 地域のわけ方、使い方のルールを決める。
- 広がりのくくりを条例で決めるか。コミュニティ計画みたいなものにゆだねるか。
3.オンブズマン制度
1.制度の考え方として2つある
- 公的なオンブズマン制度と民間のオンブズマン制度。
- 自治基本条例で取り扱うオンブズマンは公的なものが多い。
2.公的なオンブズマン制度
- 市民の苦情を簡易な手続きで迅速に処理して、市民の権利を擁護し、区公正な行政運営があれば是正を勧告するなど、行政の適切な運営を確保することを目的とした制度。
- 発祥は北欧スウェーデン。議会に代わって官僚制を統制するための憲法上の機関としてはじめて設けられ、各国に波及している。
- 任命は市長。費用負担も行政。
- 自治体オンブズマンは公的な機関となる。
- 福祉や介護など特定の分野に限って設置することもある。
- 行政側の任命だと、公正な取り扱いが保障されないような気がする。
- 独立性が担保されればそのような危惧はない。
- 任命が行政側にあり、金も行政から出るとなると、制度的に公正に運営される保障があるのか。
- 行政から法的に位置づけられ、権限も持っていることが問題解決の保障になる。
- 行政から任命されたからといって中立性、公平性には問題ないと思う。
3.民間のオンブズマン制度
- 官官接待などを問題にした市民のボランタリー的な活動のオンブズマンがある。
- 運動的に市政運営を監視する方法である。
- 権限もないのに、行政運営が改善される保証がない。