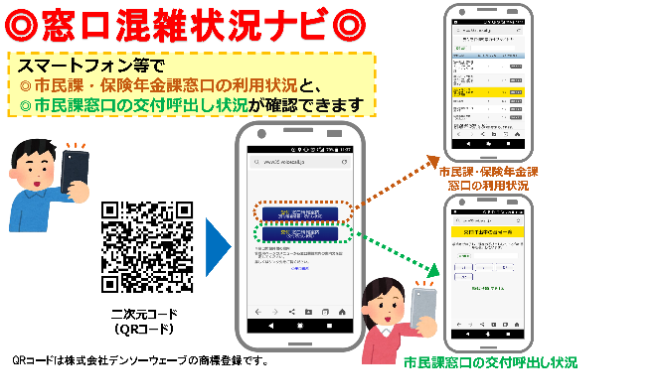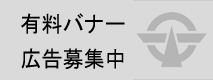第2部会 検討の記録(1)
更新日: 2007年(平成19年)10月3日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成19年5月12日(土曜)、午後7時00分~9時15分
検討テーマ
- 副部会長の選出
- 今後の部会予定日の決定
- 部会の役割について
検討の記録
1.副部会長の選出
2.今後の部会予定日の決定
5月(1回開催)
25日(金)19:00~ 福祉会館
6月(3回開催)
2日(土)19:00~
15日(金)19:00~
23日(土)19:00~
7月(2回開催)
7日(土)19:00~
18日(水)19:00~
※27日(金)19:00~全体会~
8月以降の進め方
- 8月以降は全体会の議論を通じて全体の共通認識化を進めることが必要という意見と、全体での議論よりも分科会での議論を優先し、個別の検討を深めるべきという意見の両方が出た。
- 8月以降の部会スケジュールについては、今から開催日を決めず、柔軟に考えるべきではないか。
3.部会の役割について
1.策定の手順
最初はテーマ(条になるもの)から出して検討を進めた方が効率的だ。フリートーキングでまた1から始めるのは非効率。
- テーマを先に出し、その雛形を元に1つずつ議論を深めるやり方にする。
2.検討の素材
A.他事例の使い方
- 他事例を勉強するのも良いが、実際他事例を見ても面白いと思えるような特徴を持ったものは少なく感じる。今回の検討では参考程度にした方が良い。
B.今後の検討の素材
- 1月~3月に検討した意見結果を活用できないか。
- 何か論点がまとまった資料があると良い。
- 他事例を参考にテーマをまとめた資料がある。
○資料をたたき台にする(資料のうち「首長・職員・執行機関」と「自治体運営」をこの部会の検討対象とする)。
○またテーマは30個ほどあり、一度に議論すると話題が拡散してしまう恐れがある。毎回10個ずつテーマを選んで1つずつ検討を進める。
○1~3回の意見については小平市のまちづくりの方向性を検討する上での素材として活用したい。
C.既存条例の勉強について
- 既存条例は何を読むべきか?全て目を通すべきか?
○小平市には何百の条例があるので全て目を通すことは難しい。 ○各自が気になったところについてHPなどで確認することにする。
3.検討範囲(他の法令・制度に関わる領域に対する取り扱い)
- 条例の検討では、
「レッドゾーン(他の法令・制度にふれる領域)」、
「イエローゾーン(自治基本条例での規定内容を他の法令・制度と調整が必要な領域)」
「ブルーゾーン(自治条例で規定すべき領域)」
の3つの領域が考えられる。 - 今回の検討では私たちが考える「小平らしさ」を議論する。その中で「レッド(イエロー)ゾーンだから」といって最初から検討範囲を削るべきではない。
○私たちが条例で入れたいと思う項目は全て入れる。
○もし他の法令・制度に触れるレッドゾーンやイエローゾーンにかかりそうでも検討対象とする。
○法令との調整事項についてはその後の全体会などで対応すればよい。
4.他部会との重複領域
- 第2部会の検討範囲に関係が深い他部会との重複領域については、以下のような点が想定される。
○「情報公開」
(市民の視点(第3部会)では「情報公開させる」、行政の視点(第2部会)では「情報公開する」となる。)
○「オンブズマン」
今は第1部会に入っているが行政が制度としてオンブズマンを設けることも考えられる。
制度としては[1]自治条例で規定、[2]独立したオンブズマン条例の策定が考えられる。(どちらにするかは小平市の実態に合わせて判断が必要。)
○「条例の進行管理のための組織設置」
5.検討内容
A.小平らしさはどう出すか?
- 他事例で規定していないような項目をいれてはどうか?(例;市長の多選禁止など(レッドゾーンかもしれないが))
B.市職員の位置付け
- 条例を検討する時には市民の立場からだけではなく、市職員からの立場に立って検討することが必要ではないか。
- 市職員は公僕であっても奴隷ではない。市職員にもできることとできないことがあることを踏まえて考えるべき。
C.外部委託問題
- 委託の実態とその成果についてはあまり検証されていない。不透明である。モニタリングが不十分。
- 金額に見合った成果がでているかなど、モニタリングを進めることが重要ではないか。
D.「小さな組織化」による弊害
- 職員を減らし小さな組織化を目指す中でサービスの制限や再任用制度による労働条件の悪化など、弊害も出てきている。
- こうした弊害についても目を向けるべきではないか。
E.契約制度について
- 行財政プランの検討の際に契約制度の見直しについてでていたはずだがその後何も動きがない。
F.検討の進め方
- 議論を深めると専門性が高くなる。そうなると参加者の中には議論についてこれる人が少なくなるのではないか。心配である。
- 検討の楽しさを生み出すにはどうしたらよいのか。
- 継続した参加をするためにはやはり「思い」が必要だ。思いがないと続けることはなかなか難しい。
4.次回について
1.日程
- 次回は5月25日(金)19:00~ 福祉会館
2.検討内容と方法
- 次回は資料の「首長・職員・執行機関」の始めの10項目程度について検討する。
- 検討シートとして「首長・職員・執行機関」と「自治体運営」の項目を並べた模造紙を準備する。(担当:地域研)
3.宿題
- 資料をもとに各自がテーマについて考えてくる。(追加のテーマはないか。また、各テーマに関する方向性など)
- 検討した結果を次回メンバーに配りたい人は2日前までに事務局にメモを提出。(希望者のみ)
4.欠席者対応
- 今後の開催日程、宿題メモ、検討シートを欠席者に事前配布する。
- 資料は地域研が作成し、宿題メモと検討シートについては事務局を通して部会長に確認する。(開催日程は全部会分の日程をまとめた共通資料で対応)