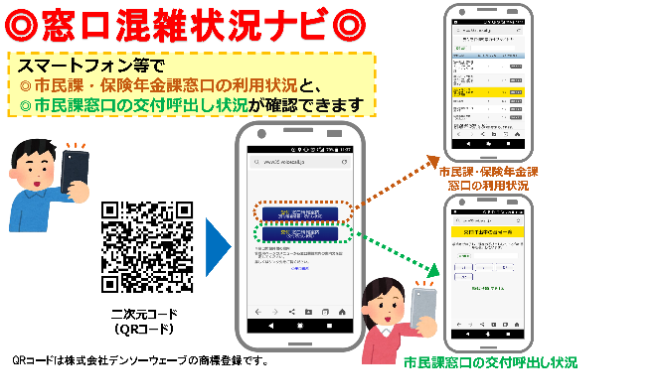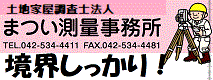第2部会 検討の記録 (3-1)
更新日: 2007年(平成19年)10月3日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成19年6月2日(土曜)、午後7時00分~9時15分
検討テーマ
- 「市長・職員・執行機関」について(続き)
配布資料
- 前回の記録
- 法律に規定がある事項(メンバー作成)
- 基本条例に精神として盛り込みたい考え方(メンバー作成)
検討の記録
1.他の法令で規定されている内容を今回の条例に載せるべきかどうか?
【問題提起】
(資料「法律に規定がある事項」の説明)
- 憲法や法令との関係性を整理した。
- 他の法令で規定があるものについて、今回の条例ではどこまでいれるべきか?
- 憲法で決まっていることを条例に全部入れるとかなりの量になる。かといって、載せるべき内容を取捨選択するための判断も難しい。
【出された意見】
■載せる
- 他の法令に規定されているから基本条例に載せないと安易に判断するのではなく、条例化する中で「政策法務」として必要なものは積極的に条例に載せるべきではないか。
- 「政策法務」とは、私たちが大切にしているものや、やりたいものを、実現すべきものを形として示すもの。
- 他事例を見ても、他の法令に規定されている内容を繰り返し載せているところがある。
- 小平市の自治基本条例に必要なもの、大切なものは繰り返しになっても入れた方が良い。市民の憲法をつくるのだから自分たちが必要だと思うものは入れておくべきだ。
- ただし、入れる内容は重要だと思えるものを選択することが必要。
- 議会と市長との関係等、関係性を検討する中で齟齬が出るようなものについても書くべきだと思う。
- 他の法令との整合性は一度作ってから調整すればよい。
■載せない
- 「市長の権利」など、法律で決まったことは載せなくてもいいのではないか?
【まとめ】
- 他の法令に関する内容も、今回の条例に必要だと思うものは載せる。(重複してもかまわない)
- ただし、全部入れるわけではなく、必要なものを取捨選択する。
2.「行政運営」で書くべき内容
【出された意見】
- 行政運営では市民がコントロールする自治のメニューを載せたい。
3.「市長の責務」について
【問題提起】
- 市長の責務として公共施設の管理・廃止という役割があるが、学校施設など一部の管理等について、市民ができるようにすることはできるのか?
- 条例にねじ込まなければ実現しないのであれば、今回の条例案に載せるべき
【事務局からのコメント】
- 学校等の教育施設について、市長ではなく教育委員会が管理をしている。
- 許可なく勝手に施設を転用することはできないが、空き教室の利用等、あいているスペース等許可がでれば教育以外の目的での利用も可能になる。
4.「6.総合的・効果的な自治体運営」について
【出された意見】
- 「市民の受益と負担」の関係を明確化し、その内容を条例に明記したい。 (情報の把握・公開・合意形成)
- この内容は第3部会(市民参加)で入れるべき内容では? ⇒一方、行政側からの視点で入れてもいいという意見もあり
5.「10.条例遵守・理念の実現」について
(1)市の条例全てについて「見直し」の規定を入れたい
【出された意見】
- 条例については、策定後の時代変化等を受けて問題もでてくるはずだし、それを改善することも重要である。
- 条例よりもそこに盛り込まれている政策の方を見直すことを重視した方が良いのではないか。(条例は政策を運用するための「入れ物」だから。)
- 他市では市民参加により見直しを検討する例もある。
【まとめ】
- この10.の項目で入れるべきか、それとも別の項目で入れるべきか今後検討する。
(2)積極的な条例化による行政運営い
【出された意見】
- 政策実現のために、条例化を積極的に進めるべき。要綱ではなく条例化。
6.「11.職員管理・育成」
(1)職員への報奨について
【出された意見】
- 小平市の職員は良く働いている。(昼休み時間の窓口業務の導入も他市と比べて早かった)
- 庁内のインセンティブ(福利厚生)として職員に「交際費」を出してもいいのではないか。
- 福利厚生については全国的に問題になっている。また、職員に交際費は出ない。交際費の変わりに報奨金など出してもいいのではないか。
(2)正規職員と臨時職員の差について
【出された意見】
- 正規職員と臨時職員の給与・身分補償の差が問題になっている。
- 臨時職員は正規職員より働いているという実態もあるようだ。実際に臨時職員は同じ職にずっといるので経験の差が出てくる可能性は高い。
- また、組織の中で問題意識のある人とない人はどうしてもでてきてしまう。
- 職員の主体性を促すことも必要ではないか
(3)緊急時のための職員配置について
【出された意見】
- 地震時の避難所近くに職員を定期的に確保してほしい。
【小平市の現状】
- 市内在住の職員は全体の約4割弱。できる限り緊急対応できる体制を整えているが、それ以外は周辺自治体との連携をとって対応する等の方策をとっている。
(4)“公僕”としての役割を職員が果たすためのサポートについて
【出された意見】
- 職員の仕事は多様化しているが人数は減っており、職員の負担が多岐にわたっている。
- 職員が本来の資質を発揮しようとしても日常の摩擦の中で疲弊してしまう。
- 疲弊する原因は業務内容によってさまざまだが、その職員のためのサポートができる人がいない。
- 制度的には代休制度はあるが他業務の関係で休みはなかなかとれない。
- 市民の負担に応えるためにも健康的なサポートにより職場環境の維持が必要だ。
- 市長は職員の負担を踏まえた上でサービスの維持を考えるべき。
- 「職員は公共に携われるべき「市民」である」働く場所が中か外かだけ。職員は市民にとってパートナーでありお客ではない。
- いっていることはわかるが考え方が哲学的で条文化するのは難しいのでは。職員が行政運営を支障なく遂行してもらうための職場環境づくりをするということならばいえるのではないか。
- 「職員は市民の財産である」という内容を入れたほうが良い。 例えば緊急時等で職員がコントロール役をしてそれをもとにボランティアが動くというように、協働で動くべき時の実際の役割分担が見えるといい。
⇒職員が“公僕”としての役割を果たすためにどのように市民と関わりを持つか?
【まとめ】
- 職場環境づくりの観点から載せる。
(5)職員がいい仕事をするために
- 職員はいい仕事をしたいという気持ちは持っているが、財政面上の枠があるためなかなか思うような仕事ができない。
- 職員の善意だけではなく制度として今回の条例にいれてはどうか。