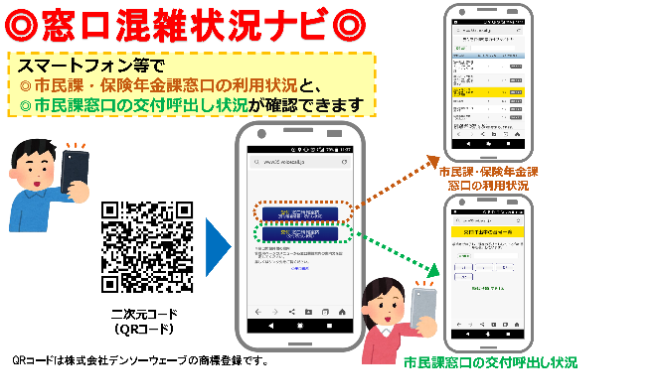第3部会 検討の記録(1)
更新日: 2007年(平成19年)10月3日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成19年5月12日(土曜)、午後7時40分~9時30分
検討テーマ
- 市民活動、地域活動に関連した自己紹介
- 小平市行政と市民参加について
- 部会の進め方
配布資料
- 「第3部会対象テーマ・いくつかのキーワード」
- 「小平市市民参加の推進に関する指針」
検討の記録
1.市民活動、地域活動に関連した自己紹介
1.自己紹介
- 市が公募した中央図書館の嘱託職員を務めていた。それ以外は、市民活動の経験はなく、今回初めて手を挙げた。
- 自治というのは、コミュニティや市民の活動から発展していくものと考えている。この会議への参加は市民としての責任ではないか、と考えて参加した。
- 行財政再構築プランの委員会に参加したのが最初。自治基本条例はまったく未知の分野であるが大変意義のあることと考え、参加した。
- 会社勤めをしながら、2003年の長期総合計画まちづくり会議に参加し、翌年に市民提言書をまとめた経験がある。
- 緑や環境の基本計画の委員、また緑化推進委員などを通して、市行政と深く関わってきた。地方分権化によって「おらがまちはおらがつくる」というスタートラインに立ったと自覚している。行政とたたかうのが好きな性分だ。
- 市民活動といえば、自治会活動を数回やっているだけのまったくの素人である。
- 長期総合計画まちづくり会議が市民活動の始まりだ。大きな目標があるわけではなく、市民参加の場がどのようなものなのか知りたくて参加している。
- 2年前までは寝に帰るだけの市民であったが、ひょんなことから福祉に興味を持った。経営改革市民会議、行財政再構築プラン委員会などに参加したのを発端に市民活動を続けている。自治基本条例は、制定基本方針が出たころから注目していた。
2.小平市行政と市民参加について
1.自治基本条例の発端
- 小林市長に変わってから公募の市民会議が積極的に開かれるようになった。
- 自治基本条例策定は、小林市長のマニュフェストが発端だと思われているようだが、それ以前に議会から声が上がっていたようだが、前・前田市長は「地方自治法があるから自治基本条例はいらない」と発言したと聞いている。
2.地方自治について
- 前田市長は堅実で、変動を好まないタイプ。地方分権の変革の波に乗らず、他の自治体から比べて遅れをとっていた。
- 今、小平市も期が熟したといえるのか?
- 「機会が熟した」といえるだろう。自治基本条例づくりは流行のようなものだ。
- なぜ自治基本条例が必要なのか、文献を見てもよくわからない。ニセコ町は2000年の地方分権法より先に条例を制定している。地方行政の実態が国より先に動いたということだろう。
3.行政について
- 社会が動くのと合せて、行政法や行政自体が固定概念にとらわれず変わっていくべき。
- 歩道の危険箇所に関して苦情を言ったら、市職員は屁理屈と聞こえるようなことを言って埒が明かなかったのに、東京都は迅速に対応した。市行政は市民生活の問題に対する意識革命が必要だ。
- 審議会の決定権について議論したい。
- 「協働」というテーマがあるが、抽象的な概念にとどまらず、行政と市民の関係を今までとは違う切り口で捉えていく必要があると思う。
3.部会の進め方
1.日程について
- 原則として、第1土曜昼間と第3土曜夜間を設定した。
- 5月26日(土曜)19:00~
- 6月2日(土曜)14:00~、16日(土曜)19:00~、23日(土曜)19:00~
- 7月7日(土曜)14:00~、21日(土曜)19:00~、27日(土曜)全体会
2.進め方
1.進め方について
- 7月27日までにかならずしも完璧にまとまっていなくていいのでは。
- 配布資料にもあるが、いくつかのテーマがある。これらは互いに関連しあう部分もあるだろう。
- あらかじめ、話したいことをメモにして持ち寄ったらどうか。
- 各回、宿題があると効率的だ。
2.検討材料と議論の入り口について
- 1~3月の意見集、他の事例という材料がある。1~3月の意見は、ひとつずつ見ていくわけにもいかないので、各自頭の中に入っているものを引き出せばいい。
- 他事例を読み込むのは時間がかかる。ひとつずつ分担して読み込んでくるというのはどうか。各論ではなく、大きな骨子を頭に入れておくような読み方でいい。
- 1~3月は「自分たちが何をしたいか」を話し合ってきた。それらの意見が、条例のキーワードのどこに分布しているのかを見たらどうか。また、その後、他事例を参考に足りないキーワードを埋めていくといいのでは。
- 1~3月は意見の言いっぱなしだった。今後は構造的に考えなければならない。どこに焦点を当てるか、「幹」を見つけたい。
- 入り口としては、各自、この部会で焦点を当てたい部分、やりたいことなどを考えてきて、それを持ち寄ったらどうか。
3.次回の宿題と目的
- 第3部会のテーマ<市民の役割・権利義務+市民参加のあり方(情報公開などを含む)>のうち、各自が「特にどのようなことに思い入れ・関心をもっているか」についてポイントをまとめ、1人3分程度で考えを述べ合う。
- 他市のいくつかの条例から部会長がピックアップし作成した、第3部会の対象テーマに関する語彙・項目リストなどを適宜参照。
- ポイント整理の方法はすべて各人の自由。箇条書き程度のものでも、席上配布してもしなくても良し。
- 次回は、これまでの部会でやったと同じように模造紙に適宜テーマを書き出し整理する。
- 次回の目的は、皆の興味の広がりを知って、今後の進め方を検討すること。