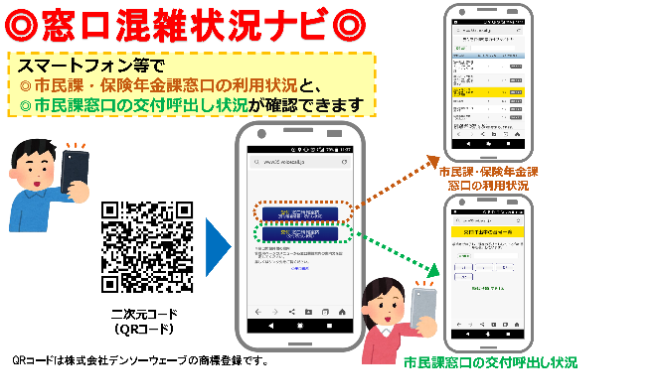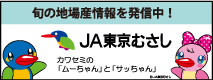第3部会 検討の記録(12)
更新日: 2007年(平成19年)11月9日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成19年8月18日(金曜)、午後5時00分~9時50分
検討テーマ
- 第3部会骨子案の詰め
配布資料
- 第三次試案
検討の記録
1.条例の「基本理念」について
【出された意見とまとめ】
・個々の条文やこの条例がなぜ必要なのかを説明するためには、基本理念を市民の会議全体として議論しておく必要がある。
・基本理念の内容によって、各テーマの方向性が変わってくる。全体で統一した基本理念が必要だ。
2.条例の「位置づけ」について
【出された意見とまとめ】
・最高規範性と、市長、市議会などの条例尊重の責務については、全体会で今後議論するテーマということで、第3部会としては提案しない。
3.市民などの「定義」について
【出された意見】
·「小平市民=小平市の区域内に住所を有する個人」とあるが、「住所を有する」とは「住民票の有無」とは関係があるのか?
·「住所を有する」の「住所」とは、地方自治法に定められている「住所=生活の本拠」のことである。必ずしも住民票がなくても「住所」と言える。
·しかし、「住所を有する」とすると、「住民票を有する」という意味だと考えてしまう人が一般には多いと思われ、わかりにくいので、「住んでいる」などとわかりやすい表現も考える必要がある。
·ちなみに、この定義でいくと、小平市内に土地家屋を所有するが、住んでいない人は「小平市民」には当たらない。(我孫子市の条例案の定義では我孫子市に土地や家屋を有する者も「市民」に含まれる。)
·「事業者等」については、小平市内に活動拠点を持っているかどうかは問わない。まちづくりの主体として、市内に拠点があるかどうかは大きな問題ではないため。
4.「参加」と「協働」の主体について
【出された意見】
·「参加」の主語は、「市民=小平市民、在勤、在学する個人、活動する個人」としたらどうか。
·しかし、具体的な市民参加の場面を想定すると、たとえば審議会では、在住である「小平市民」しか公募できないことがある。参加の主体を「市民」として広げていいのか、注意する必要がある。
·「協働」の主語は、「市民等=市民と事業者等」として、小平市のまちづくりに寄与する幅広い主体を想定している。
5.「自治の基本原則」について
【出された意見とまとめ】
·「自立した市民自治」とあるが、市民自治の形容詞として「自立した」というのはおかしいのではないか?
·条例の成果、到達点として、「自立」があるという関係ではないか。
·「自立」という趣旨の内容は、基本理念に入れ、基本原則からは削除する。
·また、ここでは、広く小平市のまちづくりに寄与する主体として、主語は「市民等」としている。
6.「市民の権利」
【出された意見とまとめ】
·「健康で文化的な生活を営む権利」については、とくに小平市在住であることを問わない、団体である「事業者等」をのぞいた「市民」の権利とする。
·「行政サービスを受ける権利」については、小平市民とそれ以外の市民では受けられるサービス内容は同じではない。(小平市民以外の市民も一定のサービスを受けている。)そこで、「法令または条例に定めるところにより平等、公平に」という表現を加える。
·事業者等も、行政サービスを受ける権利を持つが、事業者の項で別途規定する。
7.「市民の責務」
【出された意見とまとめ】
·「市政の運営及び行政サービスに伴う負担」についても、小平市民以外の市民も、何らかの負担を負っているので、「法令または条例に定めるところにより」とする。
·「自治活動への参加に当たって、自治の主体であることを自覚し自らの発言と行動に責任をもつ、互いに尊重するよう努める」責務について、事業者等も含む「市民等」が「自治の主体」であるのでこれを主語とする。
·ただし、これは単なる構成上の問題であるが、事業者等の責務については、事業者等の項に分けて記載することも考えられる。
8.情報の公開と共有
【出された意見とまとめ】
·「情報の共有」を冒頭にしたのは、これが自治活動にとって必要な基本原則であるため。次に続く、「情報の公開」と「知る権利」を考えるための前提となる考え方である。
·今までは、自治活動に必要な情報を行政が独占的に持っており、どの情報を発信するかは行政の判断にゆだねられていた。
·そのため「市政に関する情報は市民との共有財産」との表現を入れた。
·「共有」とは?「共有財産」とはどのような意味か?「財産」というからには所有権があるのか?
·⇒「共有財産」ということばは、厳密な法律用語としてではなく日常的な用語として使っていると解するべきであろう。
·「市はこれを秘匿し、または独占的に使用してはならない」というのは強すぎるのではないか?情報を市民や行政等が共有するという考え方を確認することが大事なのであり、4Bで情報をわかりやすく公開せよとか、4Cで必要な情報を請求できると規定しており、それ以上に秘匿するなとか独占的に使用するなといったといった裏返し文言まで入れることはないのではないか。
·表現を和らげた「行政の占有物ではない」とする例もあるが、抽象的であまり実効性はないのではないか。
·それよりも、情報は市民との共有財産である、したがって市民が知る権利を有し、行政は知る権利を保障する、という文脈にしたらどうか。
·また、情報を共有する主体は、事業者等も含む「市民等」とすると広すぎるため、ここでは「市民」とする。しかし、「事業者等」も、「市政への参加及び協働に必要な情報」については情報提供請求権を有するものとする(4C)。
·ここまでで時間切れとなり、部会長より、追加部会を開くか、それとも今後の取り扱い(第5章 参加及び協働 以降の部分の検討と更なる加除修正)については部会長にお任せいただくかを諮った結果、部会長が部会メンバーと協議して取り進めるということで、部会長に一任されることになった。