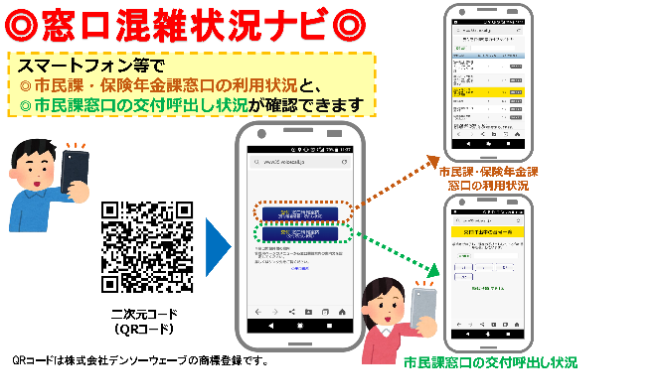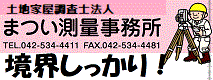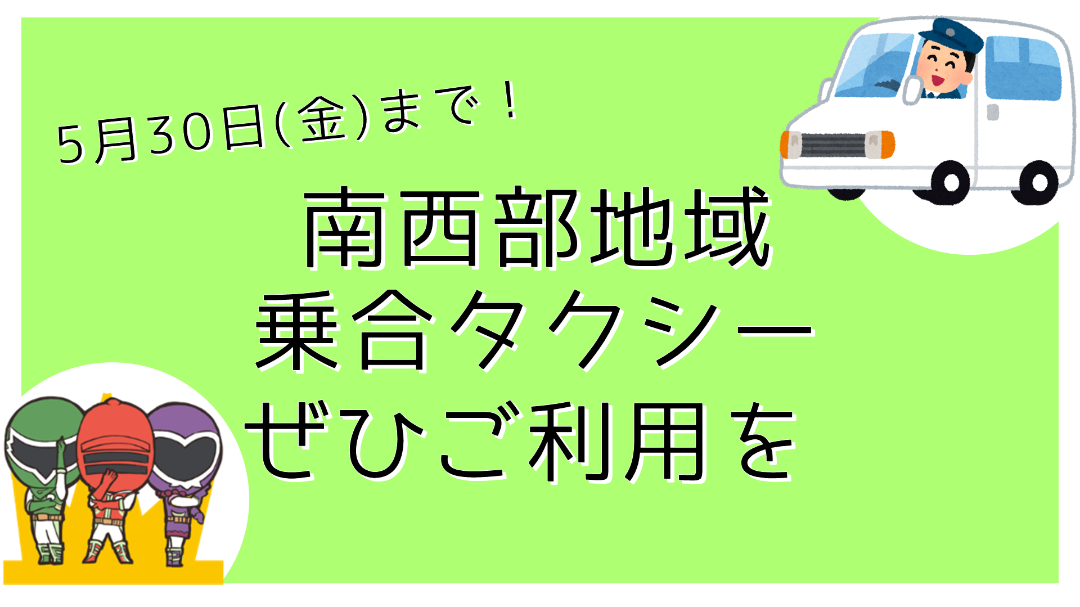平成19年度 第24回市民の会議・会議の要旨
更新日: 2008年(平成20年)3月11日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成20年2月29日(金曜) 午後6時30~8時50分
会場
健康センター視聴覚室
参加者数
20人(欠席者35人)
傍聴者:1人
配付資料
- 今後の市民の会議開催日程
- 小平市自治基本条例案のイメージ(080229現在)
- コミュニティ条項案
- 自治基本条例における市民投票の規程について(市資料)
- 小平市自治基本条例案(市議会部分その他)起草グループ(080229)
会議結果の概要
1.条文案の検討
(1)市民投票制度
- 本日は出席者が少ないので市の資料説明のみにする。
○市資料説明
○質疑
- 常設型は市民投票の発議等の設立要件により、議会の議決を経ずに住民投票の実施が出来る場合
- 非常設型は、発議や請求を受けその都度、議会の議決を行う必要がある場合
【まとめ】
- 市の資料を読み込んで、次回議論する。
(2)オンブズマンについて
○市説明
- オンブズマン制度を持つ他市の財務負担及び体制の紹介
- オンブズマンの方式は取っていないが、専門相談員が配置され、対応・機能が似ている。財務負担が大きくコストパフォーマンスの判断が必要。
- 今は必要ないが「将来必要な場合には設置」という表現は、問題と感じている。
○出された意見
- 市民相談は幅広く、オンブズマンは権利侵害への対応で質的に違う。
- (2)項表現と(1)の苦情相談の同じ表現だから判りにくい。
(3)コミュニティ
【出された意見】
- 新案#22の「集団」は地域の課題を権限もなく話し合うだけの場合のイメージ
- コミュニティの場は、地域課題の解決のためなので地域であるが、そこへの参加は幅広い団体等が参加できるように考える。
- 新#23(2)項で「市は、・・・コミュニティの設立及び連携・ネットワーク化を支援」、ここまで関与してよいか疑問
- 同(3)項、「市は、コミュニティの意見を尊重」はコミュニティ間の意見調整の場がない現在、相対立するような意見が出た場合、どう尊重すれがよいか難しいものがある。
【まとめ】
- コミュニティの定義については、旧#22の「地域を基盤とし、あるいは、共通の目的を持つ」を生かす。
- 今日の意見を受け、メンバーおよび市が対案を検討する。
議事録
今日の進め方(全体会)
1.条例案の検討
(1)市民投票制度
(2)オンブズマン制度
(3)コミュニティ
1.条文案の検討
(1)市民投票制度
- 本日は出席者が少ないので市の資料説明のみにする。
○市資料説明
- 資料を基に、各市の事例紹介
- 小平市の有権者数約14万5千人
- 請求を有権者の1/10にした場合1万5千人の署名数、1/50にした場合2900人の署名数で成立。
○質疑
- 常設型と非常設型とがわかりにくいがどのように考えたらよいか。
- 起草グループとして雑駁に簡単に言えば、市民投票実施の成立要件を具体的に定め、その要件が整う場合には、市民投票がそのまま実施される。一方、重要事項ごとに別に条例で住民投票の発議・請求権等を定める場合は、実施の判断は議会決定にゆだねられる。
- 即ち、前者は議決を経ずに住民投票が実施される場合で常設型、後者はその都度議会の議決を行うので非常設型となる。
- 議会の議決を必要とするか、必要としないかで判断するとよいと思う。
【まとめ】
- 市の資料を読み込んで、次回議論する。
(2)オンブズマンについて
○市説明
- オンブズマン制度を持つ他市の財務負担及び体制の紹介
○藤沢市
週3回相談を実施。弁護士2名で対応(月60万円、年間720万円)、市事務局、常 勤2名(年800万として、年間1,600万円)、専門調査員(100から200万円)年 間おおよそ 2500万円
○三鷹市
週1回相談を実施。
弁護士1名、準教授1名で対応。(月41万円、年間490万円)市職員2名常勤(兼 職)
- 内容が専門的になると専門相談員(資格を有している人)が当たる。
- 都内で導入しているところは、福祉オンブズマンが多い。
- 事例の三鷹市、藤沢市では市民相談制度とオンブズマン制度の両方を持っている。
- 藤沢市の場合は、事務局を別に持っている。その分、職員の配置や費用が大きくなる。
- 市の現在の市民相談(苦情・相談)の仕組み
一般相談(年531件、専門職員で対応)
法律等の特別相談(年1,355件、弁護士等の専門相談員が対応 年予算約500万円) - この制度について、市としてはオンブズマンという方式を取っていないが、専門相談員も配置されており、対応や機能が似ている。
- オンブズマン制度を考える場合、コストパフォーマンスを考え小平に必要なのかの判断が求められる。
○出された意見
- 市民相談は幅広く、オンブズマンは権利侵害への対応であって、質的に違う。
- 直ぐ造れといっているわけではなく、「必要な場合には」といっているのであって、問題ないと思うが。
- (市)先ほどの説明以外にもう一点条文で問題に感じているのは、今は必要ないが「将来必要な場合には設置」という表現は、仮定であり、条文に適さないのではないかという問題を感じている。
- オンブズマン制度の前提を整理する。現在の条文では「将来必要となった時に設置」というもので、その発議は行政又は議会である。
- オンブズマン制度はそもそも弱者の権利侵害の制度を議会が決定したところから始まっていて、議会発議でのオンブズマン設置は想定しにくい、行政発議になるだろう。その点で、条文の中に盛り込んでおくことが必要と思う。
- オンブズマン制度は条例で位置づけなければならないのではないか。
- 今後何が起こるかわからないので、(2)が入った。(1)の苦情相談の同じ表現だからわかりにくい面もある。
(3)コミュニティ
○代表
- 前回の検討を踏まえて、資料コミュニティ条項案が出たので、説明を受け、これをたたき台に検討する。
【出された意見】
- 新案#22の2行目の「集団」とはどのようなイメージか。前回意見のあった場と考えてよいか。
- 限定的に規定しないものとして使用している。前回話した都市マス策定の地域別検討を行ったときのこまち懇談会のようなもので、権限もなく話し合うだけの場合のあるようなイメージで考えた。
- 前回と今回で大きく内容が変わっている点がある。 新#22の、「~、地域を基盤とし、共通の目的をもつ市民同士により、~」で、旧#22では、「~、地域を基盤とした、あるいは、共通の目的をもった・・・」であった。新では「地域を基盤とし、(かつ、)共通の目的をもつ・・・」となり、対象をより絞り込む内容になっている。旧では「・・・、あるいは、・・・」と、並列的に述べ、対象を広げている。
- 例えば、全市等の広い範囲で活動している団体が、ある地域の問題解決に参加し、活動する場合を想定したが、新の「かつ」の場合では参加の対象になるのか、旧の「あるいは」の場合はどう考えたらよいのか。
- 新は「地域を基盤とし、かつ、共通の」だから、地域を基盤条件となり入らない、旧は「あるいは」ではいる、といえる。
- 幅広い参加を考え、旧の「あるいは」を活かす。
- 骨子案は、「自主的に形成された」という文言があったが、今回の案ではなくなっている。そこは残した方がいいのではないか。
- (市意見)新#23(2)項で「市は、・・・コミュニティの設立及び連携・ネットワーク化を支援」、ここまで関与してよいか、市としては疑問を感じる。(3)項の「市は、コミュニティの意見を尊重」というのも、厳しい。コミュニティ間の意見調整の場がない現在、相対立するような意見が出た場合、どう尊重すればよいか難しいものがある。
【まとめ】
- コミュニティの定義については、旧#22の「地域を基盤とし、あるいは、共通の目的を持つ」を生かす。
- 今日の意見を受け、メンバーおよび市が対案を検討する。