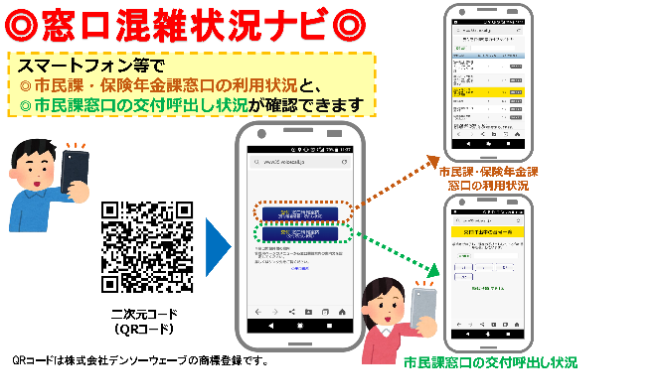小平の風とお茶(小平市の昔話)
更新日: 2021年(令和3年)1月28日 作成部署:企画政策部 秘書広報課
タマおばあさんにかたってもらうかたちで、こだいらのちょっと昔の暮らしの様子をまとめました。
風
私が小さいころは、この辺りは畑ばかりで、遮るものがないから、風の強い日は大変だったの。
そのころはどこからも富士山がよく見えてね。
「富士山に雲がかかると風が強くなる」という言い伝えもあったんだよ。
秋が深まってくると、冷たい北西の風が強く吹きはじめるんだけど、それを「おかまっ風」と呼んでいたんだよ。
その風には、「おかま様」という神様が乗っているんだって。
昔は台所にかまどがあって、薪で火を焚いていたの。
それで、かまどにおかま様という神様をまつっていたんだよ。
10月は日本中の神様が出雲に出かけていなくなるから、神無月って呼ぶんだって。
おかま様も月初めに出雲に行って、月末に木枯らしに乗って帰ってくるといわれていてね。
その風をこの辺りではおかまっ風って呼んだの。
おかまっ風が吹くと、冬支度を始めたものだね。
そのころはよく霜柱ができて、朝、学校へ行くときなんか、踏むとザクザク音がして楽しかったよ。
日中、気温が上がると、霜柱がとけて、土がどろどろになるの。
それを繰り返していると、だんだん土がかさかさになっていくんだよ。
春になると、その土で突風が巻き上げられて、吹きつけられてくる。
風が土ぼこりで赤っぽく見えるから、この辺りでは、「赤っ風」って呼んだんだよ。
土ぼこりまじりの強い風が吹きつけて、外にいたら、目なんか開けていられない。
鼻や耳の穴にまで土ぼこりが入るんだよ。
風が強い日は、戸を閉めきっていても、隙間から土が家の中に入りこんでくるの。
「障子の桟にごぼうの種がまける」というぐらい土ぼこりがたまっていたんだよ。
掃除機がなかったころは、畳の上にお茶殻の生乾きにしたものをまいて、座敷ぼうきで掃き集めていたんだよ。
雑巾で拭くと、畳の目に細かい土が入りこんで、取れなくなってしまうからね。
一日に何度も何度も掃除をしなくちゃいけないから、本当に大変だったよ。
お茶の木

今、青梅街道や五日市街道などにけやきの大木がところどころに残っているけれど、防風林として植えたものなんだよね。
畑もね、風が強いと、土が吹きあげられ、作物の上にかぶさるから、育ちが悪くなるんだよ。
土が飛ばないように、畝と畝の間には竹や笹、藁を置き、畑では間隔をあけて横一列にお茶の木が植えてあったの。
お茶の木は腰ぐらいの高さだから、風よけだけじゃなくて、作物の仕切りにもなっていたんだよ。
畑に植える木だから、あんまり大きくすると、日陰になって、作物がよく育たなくなってしまう。
だから、お茶の木は仕切りにもってこいなの。
それに風通しがいいから、いい茶葉が育つの。
お茶の木の根元には、ときどきウサギやキジもいたよ。
畑は吹きさらしだから、お茶の木が隠れ場所にちょうどよかったんだよね。
お茶

お茶の木がたくさんある家では、茶摘みに近所の人を頼んだり、子どもたちも手伝って、それは大忙しだったのよ。
ずっと昔は、「茶摘み休み」といってね、学校が一週間ぐらい休みになったそうだよ。
摘んだ葉はお茶屋さんが夕方になると集めにきて、一貫(約3.75キログラム)いくらで買ってくれるの。
農家にとっても貴重な現金収入になったし、子どもたちも小遣いがもらえるから、一生懸命、手伝いをしたんだよ。
自分のところで製茶する家もあったね。
私のおじさんはお茶を作るのが上手だったから、おじさんちには製茶専用のかまどがあったの。
だからうちではいつも頼んで作ってもらっていたの。
お茶作りは力がいるから、男の人の仕事だった。
炭火をおこして、和紙を貼った畳半畳ほどもある焙炉の上で、作り手が上半身裸になって、お茶の葉を手でもみながら作るんだよ。
熱くなった茶葉を素手で揉むんだから、大変な仕事だった。
焙炉も使っているうちに和紙が火で焼け焦げてしまうから、糊で何度も貼り直したんだよ。
それには新しい和紙はもったいないから、使い古しの和紙なんかを使ったの。
だから人に頼んで作ってもらうときも、摘んだお茶と一緒に和紙を持っていったんだよ。
農家ではお茶をよく飲んだね。
10時と3時には、お茶休みをしたよ。
昔はお茶休みのことを「こびる」とか「おこじゅ」っていったそうだよ。
農作業は重労働だったから、何かちょっと食べないと、体がもたないんだよね。
お茶うけには、里芋やさつまいもなど自分のところで採れたものを食べたんだよ。
夏にはトマトやきゅうり、すいか。
秋には柿や栗なんかもあったね。
たまにはよそで饅頭や団子を買うこともあったけど、うちで作った焼き餅やご飯団子なんかも食べたよ。
焼き餅っていうのは、お餅じゃなくて、小麦粉を水で溶いて焼いたものなの。
ご飯団子は残りごはんに小麦粉を入れて団子にしたのを、焼いたり茹でたりしたもので、どっちも簡単にできるんだよ。
味噌や醤油、砂糖をつけるとおいしいんだよね。
お茶休みだけじゃなくて、食事のあともお茶を飲むので、お茶は生活に欠かせないものだったよ。
(注)市報こだいら2014年1月1日号から抜粋。
市報こだいら2014年1月1日号 こだいらちょっとむかし(PDF 918.5KB)
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。![]()
Adobe社のサイトからダウンロードできます。(新規ウィンドウが開きます)