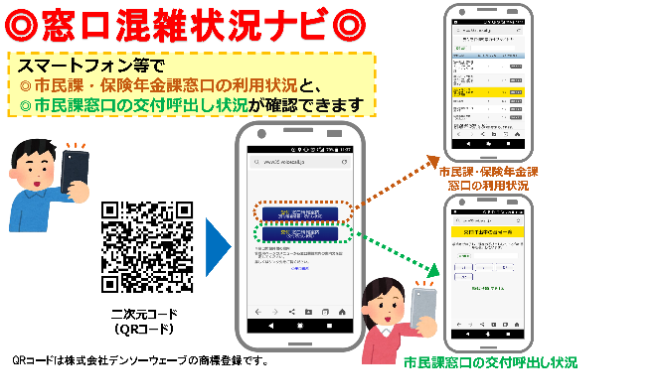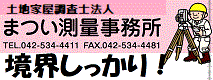赤ちゃんのお祝い(小平市の昔話)
更新日: 2021年(令和3年)1月28日 作成部署:企画政策部 秘書広報課
赤ちゃんが生まれて一歳になるまでのいろいろなお祝いごとを、タマおばあさんに語ってもらいました。
帯祝い、お七夜

お腹に赤ちゃんができると、元気に生まれてくるように、昔は腹帯をまいたの。
犬はお産が軽いっていわれていてね、安産を願って、五か月目の最初の戌の日から腹帯を巻き始めたの。
帯祝いっていうんだけど、出産する娘のことを思って実家から腹帯が届いたんだよ。
赤ちゃんが生まれて七日目には、お七夜のお祝いをしたの。
半紙に赤ちゃんの名前を書いて、高い所に貼ってね、お赤飯やお煮しめなんかのごちそうを作って、みんなで祝ったんだよ。
仲人さんや実家の両親、近所の人たちを呼ぶこともあったね。
お七夜の午前中には、おばあさんが赤ちゃんを抱いて、雪隠参りをしたの。
雪隠というのは便所のことなんだよ。
家の中にも外にもあったから、昔は回ったんだよ。
赤ちゃんが一生お世話になるところだからって、塩や酒で清めてお参りしたんだよ。
家によっては、便所のほかに井戸やかまどにも参ったんだよ。
井戸に落ちませんように、かまどでやけどをしませんようにと願ってね。
ほかにも家の上の用水路(小川)などにお参りした家もあったの。
そのとき赤ちゃんには、麻の葉模様の産着を着せて、頭には新しいおむつをのせたんだよ。
麻は強くて早く伸びるから、子どもがすくすくとじょうぶに育ちますようにという願いが込められているんだね。
お宮参り、お食い初め、初誕生

男の子は三十一日目、女の子は三十三日目に、氏神様にお参りしたんだよ。
その家のおばあさんが赤ちゃんを抱いて、お嫁さん(赤ちゃんのお母さん)と一緒に行くんだよ。
昔は男の人は行かなかったね。
この日には、お赤飯を炊いて近所の家に配ったんだよ。
実家の両親を招いて、煮しめや天ぷらなんかのごちそうをしてお祝いをしたの。
この辺りでは、ごちそうの最後には、必ずうどんを食べたよ。
百日目には、お食い初めをするの。
赤ちゃんのために、新しいお茶わんや箸をそろえ、白いご飯と魚、味噌汁や煮物なんかを作ってお祝いするの。
まだ本当には食べられないけど、食べさせるまねをしたんだよ。
白いご飯の代わりにお赤飯の家もあったね。
お膳には、きれいに洗った小石を皿にのせておくの。
歯固めといって、その石をかませるまねをしたよ。
歯が丈夫になって、石のように固いものでもかめますようにという意味なんだよね。

赤ちゃんが誕生日を迎える前に歩き始めると、足腰が弱くなるとか、落ち着かない子になるって、いわれていたんだよ。
だから一升瓶を風呂敷を包んで背負わせたの。
一升餅というのは、一升のもち米で鳥の子の形に作ったお餅のことなんだけどね。
それを背負って転ぶと、子どもに力がついて足腰がしっかりした、落ち着いた子になるんだって。
お餅の代わりに重箱に入れたぼた餅を背負わせる家もあったよ。
羽子板、破魔弓
初めて正月を迎える赤ちゃんには、暮れになると赤ちゃんのおじいさんやおばあさん、それに親戚などから、男の子には破魔弓、女の子には羽子板が贈られるの。
破魔弓は、弓破魔ともいうけど、弓と矢を組み合わせた縁起物で、魔除けなんだって。
床の間なんかに飾ったよ。
羽子板は、藤娘や汐汲みなんかの押絵がしてあって、華やかだったの。
歌舞伎役者の押絵の羽子板もあって、大きくて立派なものが多かったんだよね。
いろんなところから、たくさんもらうから、座敷の長押にさして、ずらっと並べて飾ってあったよ。
とってもきれいだったね。
羽子板にも悪いものを追い払うっていう意味があるんだって。
子どもが無事に大きくなるように願って、みんなが贈ったんだね。
(注)市報こだいら2015年1月1日号から抜粋。
市報こだいら2015年1月1日号 こだいらちょっとむかし(PDF 1.2MB)
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。![]()
Adobe社のサイトからダウンロードできます。(新規ウィンドウが開きます)