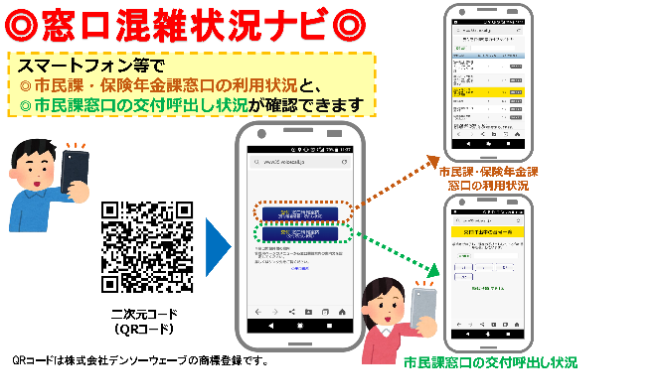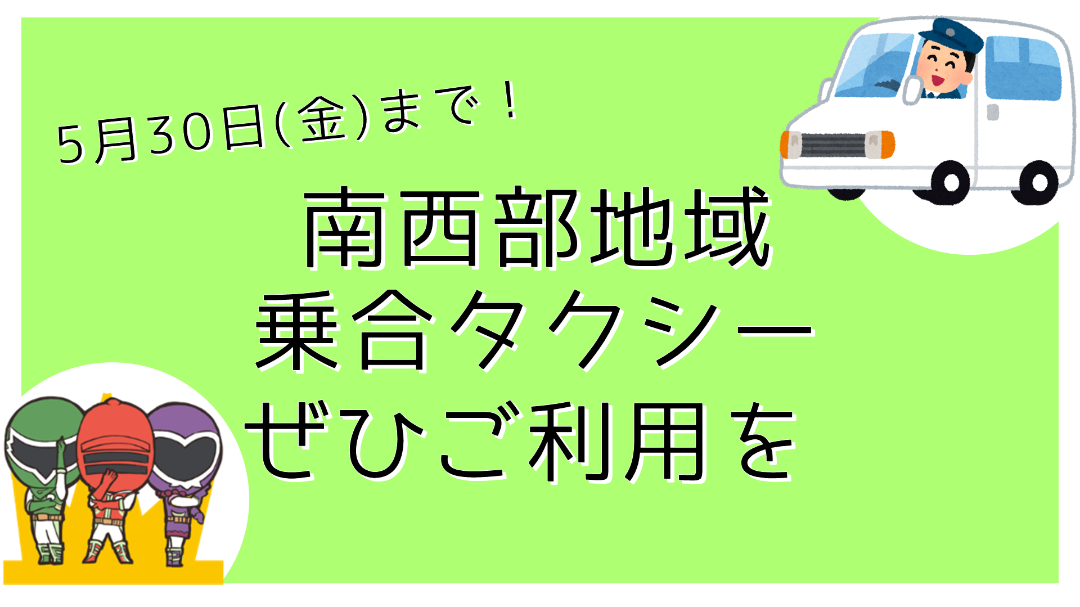第1部会 検討の記録 (4)
更新日: 2007年(平成19年)10月3日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成19年6月12日(火曜)、午後7時00分~9時15分
検討テーマ
- コミュニティについて
配布資料
- 住民自治と地域連帯を基盤とする福祉コミュニティの三層構造
- 町会と町内公民館の機能・性格
検討の記録
1.コミュニティについて
1.コミュニティの捉え方
1.コミュニティの状況
- 昔の火消しのような活動を言うのか、今なくなっているから問題にしなければならないのか。
- 住民としてなくても生活上問題になっていないのではないか。
- 今の社会は便利が主流になっている。わずらわしいと感じているのではないか。
2.地縁のコミュニティ
- 地域としてのコミュニティ
- 地域の自主性による集まり
- 資料のような福祉コミュニティはあまり考えていない
- コミュニティ組織というと町会・自治会がイメージされる
3.テーマとしてのコミュニティ
- 人と人との集団としてのコミュニティ
- 年代・テーマで人々の集まりのコミュニティ
- 連帯とか連携していく活動の社会
- 地域に限定しないコミュニティ
- まちづくり意識を持つ集まり
4.その他
- コミュニティは人と人との関わり
- 自然発生的なものが良い
- 井戸端のような場
2.コミュニティの要素
- 地域が重要な要素となるのか。
- 市民の概念に就業者を入れると、地域は前提条件にならないと思う。
- 複数の機能集団の統合のくくりと考える。
3.町会・自治会とコミュニティ
1.小平の町会・自治会の状況
- 現在市が把握している数として353団体ある。規模はさまざまである。
- 町会・自治会の連合組織はない。
- 町会・自治会などの組織率は40%程度である。
- 市から事務費補助として会員1名(1世帯)あたり100円の補助が出ている。
2.町会・自治会とコミュニティ
- 今の町会・自治会の運営は自治的活動になっていないのではないか。だから参加が少ない。
- 身近なのは町会ではあるが、今の活動に魅力を感じない。
- 町会の役員が誰だか判らないなど、情報が少ない。
- 地域で担える役割には何かと考え、自分は独自に防犯・防火の活動を始めた。今では輪が大きくなり20人ぐらいでやっている。町会はこの住民有志が始めた活動に無関心だし参加してこない。
- マンション管理組合は町会・自治会みたいな自治組織と考えてよい。
- 町会・自治会はあったほうが良いが、実際に機能しているかは疑問。
- 町会・自治会の必要性を感じない。
- しかし、地域のための活動を一生懸命やっている町会・自治会もある。例えば、火事になったとき、中に人がいるかいないか判らない状態での放水は消防として出来ない。このとき、いち早く地域の人が情報を持っていれば、対応は早くできる。そのようなことから考えても地域のつながりは必要だし、町会・自治会も同じこと。このようなことをみんなは知らない。いざというときに困ってしまう。
4.コミュニティの形成
- 防犯・防火活動を通して地域のつながりができている。このようなつながりがコミュニティ活動の基本と思う。
- 地域でセミナーや活動、署名活動などの協力の輪を作ればそれがコミュニティである。
- 自分たちのまちをどうあったらよいか考え、行動するのが自治の基本。今の町会・自治会はそのような気持を持っていない。
- 今の町会・自治会は理念がないのでコミュニティとは思わない。
- 地域の単位でまちづくりのことを考えていくことが大事。都市マスの策定で地域を7つに分けて、地域別構想を市民参加でつくったが、地域に呼びかけ、みんなで一からまちのことを考え、構想を練るようなつくり方にはならなかった。
- まちづくりの権限や経費を身近なところに落としていかないと良いまちは出来ない。
- コミュニティは緩やかな組織、人、集団の集まり。町会・自治会とはイメージが違うような気がする。
- コミュニティにはみんなが集合する場が必要。
- コミュニティをイメージしたとき、まちづくりの実施や組織維持、みんなが集まる場が必要となり、そのための経費負担が出てくる。活動する個人に負担さすことはできなくなる。緩やかな組織でこの費用や場が保障されるのか疑問。
- 活動の経費はみんなで負担するのが基本。
- コミュニティと自治会の違いは、コミュニティは個人参加が基本、しかし、町会・自治会は家単位の参加。
- 地域の市民の自主的な集まりがコミュニティ、それをどのように作るのか。
- コミュニティの機能として災害や犯罪などの防止を機能として持つと良いだろう。
- そのような機能が必要なのはわかる。機能は目的達成の手段なので、コミュニティの目的を明確にしないといけないだろう。
- コミュニティを規範的に考えるのは難しい。