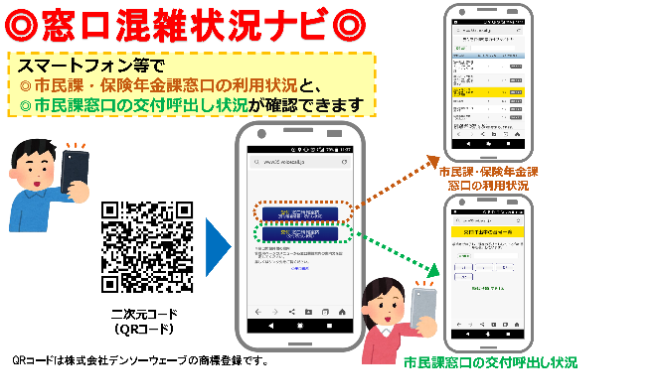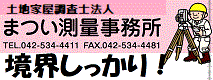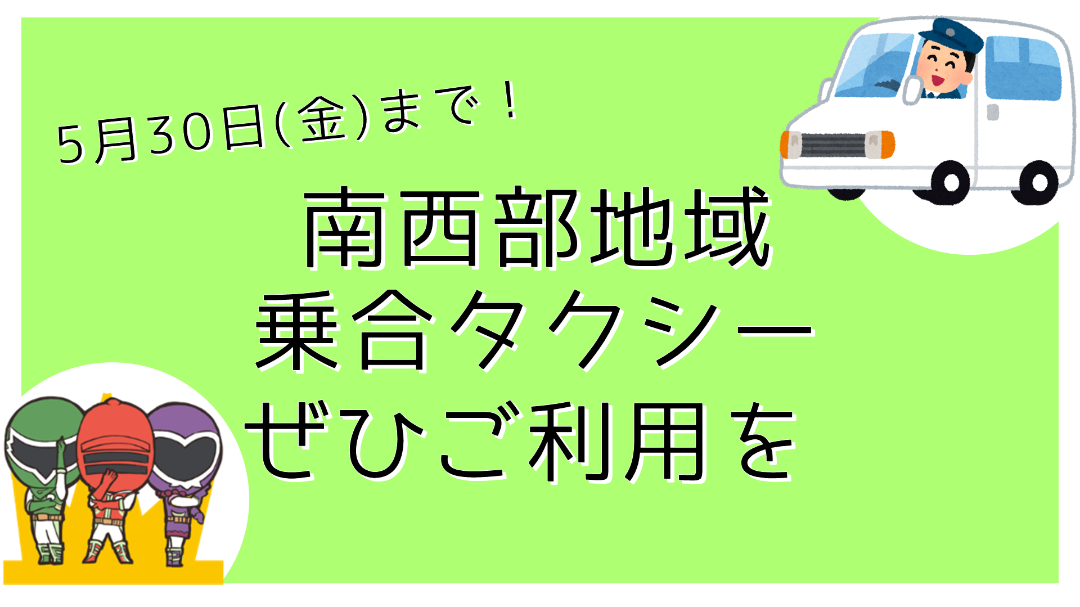第3部会 検討の記録(8)
更新日: 2007年(平成19年)11月9日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成19年7月27日(金曜)、午後7時00分~9時30分
検討テーマ
- 自治基本条例をつくる必要性について再確認する
- 「環境権」についてどう扱うか、扱えるのか
配布資料
- (仮称)国分寺市自治基本条例素案から「参加と協働」関連部分の抜き出し
- 教育委員会のしくみと仕事(全国都道府県教育委員会連合会HPから)
- 小平アクティブプラン21の抜粋(平成19年度小平市男女共同参画推進協議会検討結果)
検討の記録
1.自治基本条例をつくる必要性について再確認する
【出された意見】
(1)市民が政策決定に関わる実験の場
·地方分権の流れによって、地方自治体や市民にも権限が移譲されてきたとき、「市民にとって都合のよい」仕組みを考える、ということだと思う。
·いままでは政策の意思決定プロセスに市民が選挙でしか関われなかった。それが今回は市民が条例案を作成するところから関わることができている。このやり方、内容でうまくいくのか、社会実験の場であると考えている。
·間接民主主義に対して、このような直接の市民参加がどのような正統性を持つのか。
(2)市民が市民に訴えかける夢、主張としての条例
·基本条例は、具体専門的な個別条例とは異なり、抽象的なものであるので、根底に流れるエッセンスこそが重要で、それが各条文に共通していることが望ましい。そのため、目的規定が最も重要な規定のひとつではないか。
·自治基本条例は市民のためのもの。市民の夢、主張を表現するもの。その意味で、前文は条例のコンセプトである。多くの市民に前文で納得してもらえることが重要。
·前文と目的は、市民に訴えかけるようなものにしたい。
(3)市民が主役のまちづくりの制度化
·「市民ひとりひとりが主人公になるような政治」をしようとしている。その権利を市民は「勝ち取った」のではなく、上から「与えられた」ものだ。
·「市民が主役のまちづくり」を目標にしたい。「市政と市民の関わりの仕組みづくり」もまちづくりのひとつである。自治基本条例はそのための原則を定めるものだ。つまり、「市政に参加する権利」が最も重要だ。
·具体的な制度手続きは、下位条例や規則などに定めればよい。
·よりよい市民参加条例や協働推進条例などを作りやすくするための条例ではないか。
(4)そのための土壌づくりが必要
·しかし、「市民参加」といっても参加する市民はごく一部の限られた人でしかない。
·市民参加という場合、まず参加する市民を増やす、育てるステップが必要なのではないか。その意味では小平市においてまだ基盤ができていないのではないか。
·市政やまちに対して関心を持つ、持たせることから始めなければならないのではないか。
·たとえば、都市マスタープランなどの行政計画についても、行政案を先に出してしまうのではなく、まず関心を持たせる学習ステップが必要なはずだ。その上で市民も交えて検討するという方法が理想的だと思う。
(5)自治とコミュニティを市民自ら考える場
·個々の市民、その参加、協働などいろいろな概念があるが、「自治」を考える際には、個々の市民だけではなく、地縁組織としての自治会、町会について方向性を示したい。
·しかし、加入率の低い町会だけではコミュニティとして弱いのではないか。町会よりももっと市民を引き付ける力の強いコミュニティも合わせて考える必要があるのではないか。
·それについては、行政主導で方針を出すわけにはいかない。市民自らで考えるべき。
2.「環境権」についてどう扱うか
【出された意見】
·環境というテーマを個別には扱えないのではないか。なぜなら、環境を扱うなら他にも扱いたいテーマがあるという意見の人も多い。なぜ環境だけ特出しできるのか。
·「環境権」という言葉が使われている他事例もあるが、内容は抽象的である例が多い。
·具体的な制度で縛ると、私権の制限になるので難しいためだろう。
·「将来の世代に継承する」、「持続可能性」といった言葉で表現できないか。
·緑地は、NPOや行政ではなく、地域住民が守るという気持ちになり実際に行動しないと結局残らない。
·前文なのか、市民の権利なのかはわからないが、いずれにしても抽象的にならざるを得ないのだろう。
·小平市の目玉としても、環境については特に触れておくべきと考える。
·抽象的であっても、将来の目標やとっかかりを作ることは重要だ。