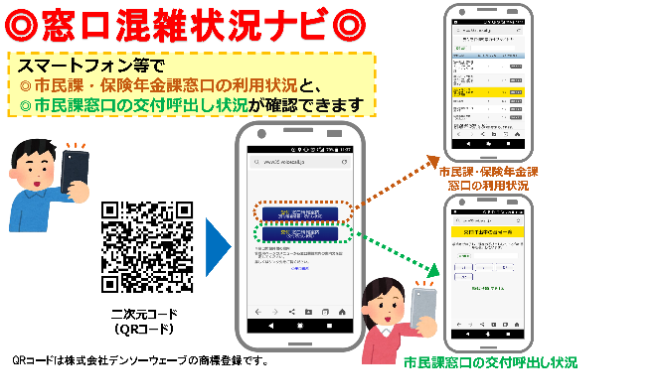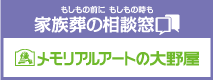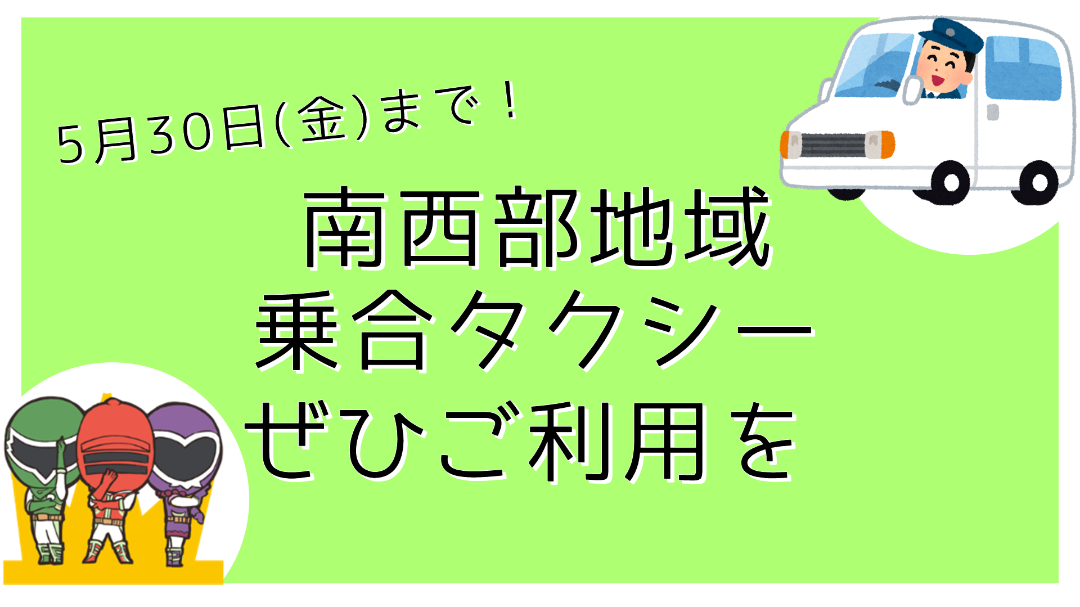市史編さんこぼれ話No.17 「ヒイラギと生け垣」
更新日: 2011年(平成23年)7月1日 作成部署:教育委員会教育部 図書館
生け垣
小平の背骨である青梅街道を歩いているとケヤキの大樹に目を奪われがちであるが、脇道にそれると家と家の境目に生け垣が植えられている。なかでも多いのがヒイラギの木である。茶とウツギ(宇津木)が、風(砂塵)除けに植えられた記録は古文書にも見られるが、ヒイラギがいつ頃から用いられているのか、はっきりしない。
ヒイラギとリース
しかし、戦争直後にはヒイラギの立派な生け垣が多くあったことは、ある学園史料室の聞書でも明らかになっている。まだリースが一般的でなかった1950年ころ、学園ではクリスマスなどに家の玄関に飾るリースを製作したという。そのおり用いたのが、このヒイラギ(正式名はヒイラギモチ)であったというのだ。その頃、小平にはすでにヒイラギの生け垣が一般的であったといえよう。
節分と鬼の宿
ヒイラギというと一般には節分を思い起こす。節分の「鬼は外、福は内」の豆撒きとともに、イワシの頭を焼いてヤキガラシをつくり、常緑の枝と一緒に玄関などの出入り口に挿しておく。その常緑の枝に用いられるのが、トゲを持つヒイラギである。小平は、そのヒイラギには、不自由しなかったといえよう。
ところで小平の「民俗」として注目されるのが、「鬼の宿」である。節分のおり、鬼を退散させる豆撒きをせずに、逃げ込んだ鬼をかくまう「奇特」な家が、小川には何軒があるのである。しかも「福は内」とはいっても「鬼は外」とは叫ばないのである。そればかりか、一晩中、家に鬼を匿い、ご馳走したうえ、早朝には家の主人がわざわざ街道の辻まで見送っていくのである。
垣内(カイト)
その見送る場所が、「境界」ないしは「結界」ということになろう。何らかの境目、ないし区切りということになる。その境界や区切りに注目したのが、柳田国男である。なかでも戦後しばらくはカイト(垣内)という民俗語彙に注目した。集落や村組などを指すことばで、コーチ(耕地)やツボ(坪)などとともに一定の領域を表す語彙である。小平では、「クミアイ(組合)」や「ツキアイバ(付合場)」ないし「サシバ(差場)」が、これに対応する民俗語彙となろう。柳田は、この民俗語彙から占有や私的所有の初源的意味の解明を試みたが、解決は残されたままである。
ブロック塀から花卉の庭園
ところで、その占有の目印は、垣根になり、いつしかコンクリートやブロック塀になってしまった。しかし、ブロック塀の危険性が地震などで指摘されるようになると、生け垣への再評価がなされるようになる。小平市は、これを積極的に支援し、緑の垣根の保全に努めた。その結果、ブロック塀の替わりにさまざまな生け垣ができるようになった。
さらに塀にも工夫がなされ、隙間から中が見えるようになり、またポットで植物が塀に飾られ、四季折々の草花が楽しめるようになっている。なかには庭園を開放する家も表れている。庭につるバラが生え、イギリス風の庭園が散歩途中に、ふと立ち寄れるようになっているのである。
占有からコミュニティーへ
花に誘われ、庭園と主との会話に花が咲き、近隣のコミュニティーの場になることも夢ではない。塀という占有が、草花の垣根や庭園に変化することで、私的所有が変化しはじめている。緑や花は空気とともに共有とまでは行かなくとも、人々の心をつなぐ生け垣になりつつあるのである。
ここ小平を散策していると、そんな光景が発生しはじめていることに気がつく。ちなみに発生とは、絶えず生じることである。このような光景が拡大するか、否かは、小平市に住む人々の心にかかっているといえよう。