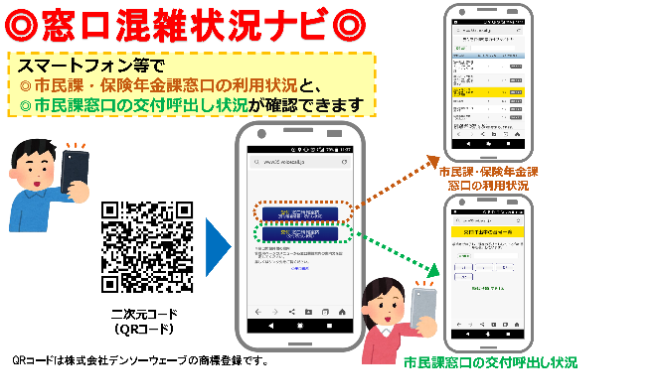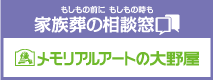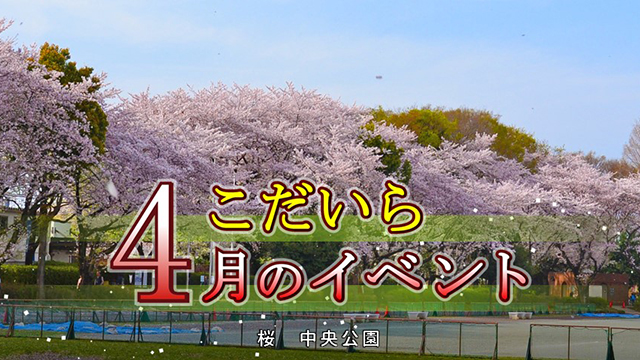違反建築物等の取締りについて
更新日: 2021年(令和3年)4月1日 作成部署:都市開発部 建築指導課
小平市では、違反建築物のない安全で安心なまちづくりを推進するため、違反建築物を防止する活動のひとつとして建築現場のパトロールを行っています。建築基準法関係規定に違反する建築物に対し、建築主、設計者、施工者等に適宜、是正指導を行います。
工事中の建築物等でお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。
なお、通報のあった建築物への調査結果等については、公務員の守秘義務(地方公務員法第34条)により原則として通報頂いた方への回答は行っておりません。ご理解賜りますようお願い申し上げます。
よくある質問
敷地いっぱいに家を建てている。
建築物を建てる敷地には建蔽率の制限があります。建蔽率の制限は、その敷地の用途地域等によって異なります。敷地いっぱいに建っているように見えても、建蔽率はそれほど高くない場合があります。
工事中の建築物の用途や規模、配置などを知りたい場合には、建築指導課(市役所4階)にて建築計画概要書の閲覧等をご利用ください。
隣家が近接して家を建てている。
一般的には、建築基準法に適合していれば、敷地境界線ぎりぎりに家を建てても違反ではありません。
一方、民法には原則として、建築物を建てる場合には隣地境界線から50センチメートル以上離さなければならないという決まりがあります。民法上の問題は裁判などでの解決となるため、法律相談などをご利用ください。
高い建物が建ち、日当たりが悪くなった。
建築基準法では、新たに建築する建築物による日影を制限するために、一定の規制を設けています。規制の内容は、用途地域や敷地の状況により異なります。
また、小平市では一定規模以上の建築物においては「小平市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」や「小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例」による手続を定めています。
隣地から雨水が流れてくる。
民法において一定の決まりがあります。民法上の問題は裁判などでの解決となるため、法律相談などをご利用ください。
隣家の窓が近くプライバシーが心配だ。
民法において一定の決まりがあります。民法上の問題は裁判などでの解決となるため、法律相談などをご利用ください。
隣家が敷地境界線を越えて建てている。
まずは敷地境界の確定が必要です。敷地境界を確定するには、土地家屋調査士などの専門家にご相談ください。
また、建築確認において土地所有権については審査の対象外となっております。敷地境界線を越えて自分の敷地に隣の建築物が入っていることが確定した場合には、裁判などでの解決となるため、法律相談などをご利用ください。
隣家にあるエアコンの室外機等の排気や騒音に困っている。
建築基準法には、設備機械の排気や騒音に関する近隣への配慮についての定めはなく、当事者同士で話し合って解決することになります。話し合いで解決できない場合は、裁判などでの解決となるため、法律相談などをご利用ください。
貸している土地に、許可なく借主が建物を建てている。
建築確認において土地所有権及び使用権については審査の対象外となっております。当事者である貸主と借主とで話し合って解決することになります。話し合いで解決できない場合は、裁判などでの解決となるため、法律相談などをご利用ください。
工事中の建築物があるが、何が建つのかわからない。
工事中の建築物の用途や規模、配置などを確認したい場合は、建築指導課(市役所4階)にて建築計画概要書の閲覧等をご利用ください。
近くの建築工事の騒音・振動がひどい。
建築工事に伴う騒音・振動については、建築基準法による規制はありませんが、騒音・振動については、公害関係の法令による規制があります。
工事による騒音・振動についてお困りの場合は、住みよい環境(騒音、大気汚染の相談)をご覧ください。
2階建てと聞いていたが、3階建てに見える。
最近は、外見からでは階数が分かりにくくなっております。小屋裏収納がある家が増えており、1階と2階の間に天井裏収納がある家もあります。
また、3階建てとして確認申請されている場合もありますので、階数等を確認したい場合は、建築指導課(市役所4階)にて建築計画概要書の閲覧等をご利用ください。
お店を開業するが建築基準法違反にならないようにするには、どうすれば良いか。
建築基準法による規制は、事業の内容や規模、予定敷地によって異なります。専門家による検討や設計が必要となるため、まずは建築士、設計事務所などにご相談されることをお勧めします。なお、建築物の新築、増築、改築はもちろんのこと、用途変更についても確認申請が必要となる場合がありますので、その点も専門家にご相談ください。
欠陥住宅かどうか、調べてほしい。
欠陥調査については、設計事務所等にご相談下さい。(一社)東京都建築士事務所協会(外部リンク)などを参考にご相談ください。